E‑E‑A‑Tの4要素を徹底解説!初心者でもGoogle検索で上位表示は可能!

Google は「安心して読める記事かどうか」をとても大切にしています。
その判断材料が E‑E‑A‑T です。
もともと3要素(E‑A‑T)だったところに、2022年に「Experience=書き手の実体験」が追加され、さらに重視されるようになりました。
つまり「やってみた結果」と「確かな情報源」の両方がそろった記事ほど評価が高くなる、というわけです。
この記事では、E‑E‑A‑T の4つの要素をかみ砕いて説明し、今日から試せるチェックリストも用意しました。
初心者の方でも迷わず実践できるので、どうぞ最後まで読み進めてみてください!
E‑E‑A‑T の4要素をやさしく解説
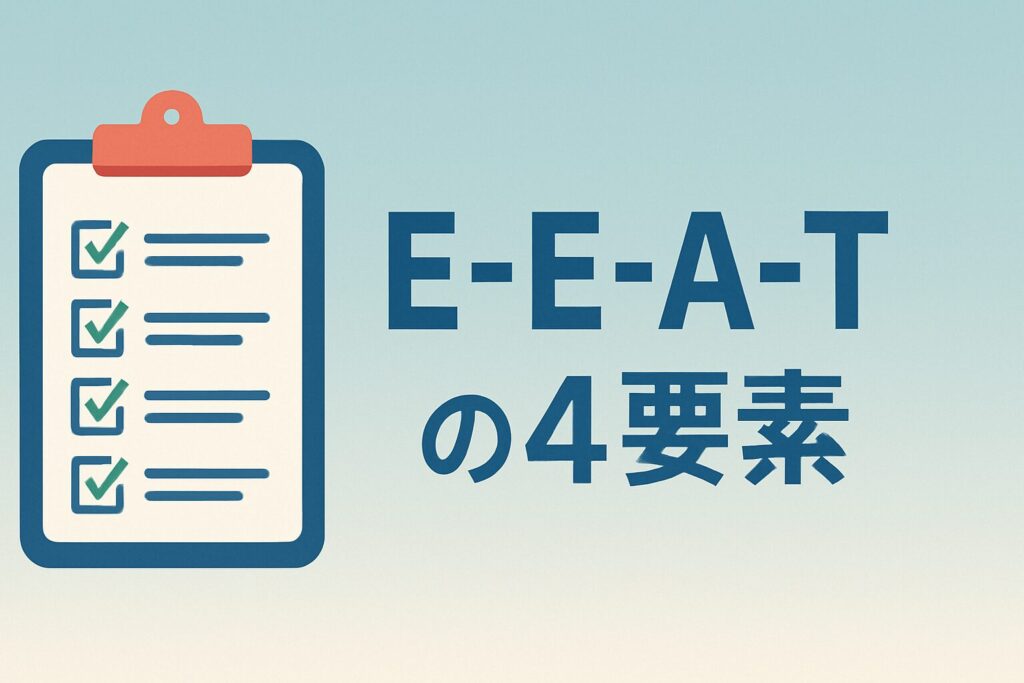
Google が検索品質評価ガイドラインの中で定めるE‑E‑A‑T は「経験・専門性・権威性・信頼性」という4つの要素で構成されています。それぞれがどんな役割を持ち、記事にどう生かせるのかを順番に見ていきましょう。難しい概念に感じるかもしれませんが、実例と一緒に解説するので、肩の力を抜いて読み進めてみてください。
※参考:Search Quality Rater Guidelines: An Overview|Google
1. Experience(経験):実体験で信頼を生む
記事に「自分でやってみた体験」を盛り込むと、文章に温度感が生まれます。
たとえば新しいツールのレビュー記事。
導入前の悩み→使い方→結果というストーリーを写真や数字付きで示すと、読者は自分が体験しているようにイメージしやすいでしょう。
また、理想的な結果だけでなく「最初は設定に30分迷った」といった小さなつまずきや、失敗から得た学びも添えるとリアリティが増します。
結果的に「この人の話は本当だ」と納得されやすくなります。
2. Expertise(専門性):深い知識で納得感を高める
記事の専門性は「どれだけ深くそのテーマを理解しているか」を示す指標です。
資格や受賞歴があればベストですが、必須ではありません。
業界歴や研究歴、過去の成功事例をプロフィールに書き、本文では専門用語をかみ砕いて説明する姿勢が大切です。
たとえば 、SEO の話題なら「インデックス=検索エンジンの図書カードのようなもの」と例えると、初学者でもスッと理解できます。
密度の高い知識をやさしい語り口で届けることで、読み手は「勉強になる」と感じ、専門家として認識してくれます。
3. Authoritativeness(権威性):第三者の裏付けで重みを持たせる
権威性は「この人/このサイトの情報は他の専門家から見ても確かだ」と外部が認めている度合いです。
たとえば新聞や専門誌に引用された実績、大学や業界団体との共同研究、行政機関からのリンク・引用などは、第三者があなたの発信を“お墨付き”と評価している証拠になります。
また、受賞歴やセミナー登壇歴、信頼性の高いサイトからの被リンクも、検索エンジンが権威性を推測する重要な手がかりです。
このような背景から、初心者がWebサイトを作っても、権威性を高めるのは簡単ではありません。
記事内で権威性を高めるには、まず信頼度の高いデータソースを使い、出典名・発行年・URLを必ず明記することが第一段階です。
そのうえで「前年に比べて○%増加」など、数字を読み解く一文を添えると、単なるコピペではなく“理解して引用している”と示せます。
さらに、専門家インタビューや公的資料を図解に落とし込むと、読者が視覚的に理解しやすくなり、記事の価値が上がります。
4. Trustworthiness(信頼性):安全性と透明性を示す
読者が安心して行動できるかどうかは、サイト全体の“透明度”に左右されます。
運営者情報や連絡先を明示し、SSL(通信を暗号化する仕組み)を導入すると、読者は「何かあっても相談できる」と感じやすいでしょう。
広告やアフィリエイトリンクを掲載する場合は「PR」や「広告」といった表記を冒頭で宣言することで、ステルスマーケティングの疑いを抑止できます。
さらに、プライバシーポリシーページを用意して個人情報の取り扱いを明示すると、読者の不安は大きく減少します。
E-E-A-Tの4つの要素は、それぞれ独立していますが、組み合わせることで相乗効果が生まれます。
たとえば、体験談に専門的な解説を添え、信頼できるデータで裏付け、運営者情報を明示する――この流れを意識すると、記事の説得力と安心感が一気に高まります。
Google が E‑E‑A‑T を評価する仕組み

Google が E‑E‑A‑T を検索順位に反映するプロセスは、ざっくり3つのステージに分かれています。それぞれの役割について、流れがイメージしやすいように整理しました。
ステージ1:人の目による評価
世界各国にいる数万人規模の「品質評価ガイドラインテスター」が、実際にWebページを閲覧して採点します。
彼らは医療・金融などの重要分野を含む幅広いテーマの記事を対象に「このページは家族や友人にすすめられるか?」という観点で E‑E‑A‑T を5段階評価します。
テスターは順位を直接いじるわけではなく、あくまで学習用データを作るのが仕事です。
ステージ2:AI がパターンを学習
集まった評価データは、匿名化されたうえで AI(機械学習)の教材になります。
アルゴリズム(検索順位を決める自動計算プログラム)は「体験談があるページは高評価になりやすい」「公的統計を引用しているページは信頼度が高い」といったパターンを数百項目以上のシグナルとして抽出する仕組みです。
こうして E‑E‑A‑T を数値化するモデルが作られます。
ステージ3:コアアップデートで反映
年に数回行われる検索アルゴリズムのコアアップデート(Google が年に数回行う、検索順位ルールの大幅な見直し)では、学習したシグナルの強さが調整されます。
その結果、E‑E‑A‑T を満たすページが少しずつ順位を押し上げられる仕組みです。
ただし E‑E‑A‑T だけがランキング決定の要素ではなく、検索意図との合致度やページ速度など他シグナルと組み合わさって総合評価されます。
覚えておきたいポイント
E‑E‑A‑T は“順位を決めるスイッチ”ではありませんが、品質評価のシグナルとして重要度が年々増加中です。体験談・専門知識・信頼データ・透明性の4点をそろえた記事は、アップデート後に上がりやすい傾向があります。
実践編:記事に落とし込む7つのステップ

E‑E‑A‑T を実際の記事にどう組み込むかを“準備 → 執筆 → 公開後フォロー”の流れで具体化します。7つのステップを順番に実行すれば、初めての人でも迷わず品質を底上げできます。ポイントは「小さいタスクに分けて一つずつ完了する」こと。では詳しく見ていきましょう。
ステップ1.体験談を書き込む ── まず自分のストーリーを置く
記事に温度感を与える最短ルートは、筆者自身の経験を最初に示すことです。
レビュー記事なら「購入前に困っていたこと→実際に使った手順→得られた結果」を3段落に分け、スマホ写真やスクリーンショットで補強しましょう。
数値化できる場合は「作業時間が 90 分→45 分に短縮」と具体的なビフォーアフターを記載します。
失敗談と学びを添えると、読者は“リアル”を感じて共感しやすくなります。
ステップ2.プロフィールを整える ── 専門性を 100 字で伝える
記事の説得力は「誰が書いたか」で大きく変わります。
筆者欄に経歴・資格・実績を100文字程度でまとめ、アイコン写真や SNS リンクも忘れずに。
たとえば「Webライター歴5年|SEO検定3級|月間20万PVの住宅ブログ運営」など、数字入りで書くと一目で強みが伝わります。
プロフィールは記事ごとに微調整し、テーマとの関連性を高めると効果的です。
ステップ3.信頼ソースを引用する ── データと専門家で裏付ける
どんなに良い体験談でも“自分だけの意見”では主観に偏りがちです。
そこで、公的統計・学術論文・専門家インタビューを引用して客観性を補います。
引用するときは出典名・発行年・URLを必ず明記し、「前年に比べて 18%増加」など数字をかみ砕いて解説しましょう。
読者は数字の背景をイメージでき、Google は出典リンクで信頼度を評価しやすくなります。
ステップ4.透明性を担保する ── 連絡先と運営情報をフッターに
読者が安心して行動できるかどうかは、サイトの“顔”が見えるかにかかっています。
会社概要・代表者名・所在地・問い合わせフォームなどをフッターに常設し、「いつでも連絡できる」状態を整えましょう。
あわせて SSL 化(URL が https で始まる)を行い、ブラウザの“保護された通信”マークを表示させると信頼度がさらにアップします。
ステップ5.広告表記を明示する ── PR とコンテンツを仕切る
PR 記事やアフィリエイトリンクを含む場合は、冒頭に「広告」「PR」という表記を置いて読者に区別を示します。
ステルスマーケティングの疑いを避けるだけでなく、Google のガイドラインでも推奨される安全策です。
加えて、リンクに rel=”sponsored” 属性を設定すると、検索エンジンにも広告リンクだと明示できます。
ステップ6.誤情報をチェックする ── 公開前にファクトチェック
原稿が完成したら、数字・固有名詞・引用リンクを再確認しましょう。
可能なら第三者に校閲を依頼し、主観的な表現や根拠のない断定がないかをチェックしてください。
無料ツール(Google Fact Check Tools など)で誤情報リストを探すのも有効です。
信頼度の低い情報が混ざると E‑E‑A‑T 全体が下がるので、公開前の“最後の砦”として徹底します。
ステップ7.読者の声を取り入れる ── 更新で信頼度を伸ばす
公開したら終わり、ではありません。
コメント欄や SNS の反応をモニタリングし、「ここが分かりにくい」「別の事例が見たい」といった声を拾って記事を更新しましょう。
更新日時を明記し、追記箇所をハイライトすると、Google から“メンテナンスされている記事”と評価されます。
定期的なブラッシュアップは、長期的な E‑E‑A‑T 向上につながる要素です。
ケーススタディ:E‑E‑A‑T 強化前後の比較
E‑E‑A‑T 対策を行う前と後で、具体的にどこまで数値が伸びるのか、モデルデータで確認してみましょう。
以下の表は、施策実施から3か月後にどのように改善できるのか、生成AIで予測したものです。
改善幅を数字で把握することで、取り組む優先度や期待効果をイメージしやすくなります。
| 指標 | 強化前 | 強化後 |
|---|---|---|
| Google 検索順位 | 25位 | 8位 |
| 平均滞在時間 | 1分12秒 | 2分05秒 |
| 直帰率(1ページだけ読んで離脱した割合) | 78% | 52% |
| ページ/セッション(1回の訪問で読まれたページ数) | 1.3 | 2.1 |
| クリック率(CTR:検索結果でリンクがクリックされた割合) | 1.4% | 3.2% |
| 被リンク数(他サイトからの参照リンク) | 4本 | 17本 |
E‑E‑A‑Tのよくある質問(Q&A)
Q1. E‑E‑A‑T を満たさないと順位が下がりますか?
A. 順位は数百のシグナルで決まるため「絶対に下がる」とは言い切れません。ただし Google の品質評価ガイドラインでは、特に医療・金融・法律などの YMYL(Your Money or Your Life)分野で E‑E‑A‑T を明らかに満たしていないページは、アップデート時に順位が大きく下がるケースが報告されています。逆に同じキーワードで競合と内容が拮抗している場合、E‑E‑A‑T を強化したページがじわじわと上位へ押し上げられる傾向があります。要するに「上がるための加点」よりも「質が足りないと減点される」リスクを防ぐ意味合いが強いと覚えておくとよいでしょう。
Q2. 実名を出さないと専門性は示せませんか?
A. ペンネームでも評価は可能です。重要なのは「実在する人物かどうか」よりも、「その分野について十分な知識や経験を持っているか」が読者に伝わるかどうかです。たとえば、ハンドルネームでも、プロフィール欄に保有資格(例:管理栄養士)、実務歴(例:病院勤務5年)、執筆実績(例:健康メディアで月10本連載)を具体的に書けば専門性は十分に示せます。SNS やポートフォリオサイトへのリンクを添えておくと、情報の裏付けが取りやすくなるためさらに効果的です。
Q3. 小規模ブログでも権威性を上げる方法は?
A. 規模が小さくても、①公的データの引用、②専門家への簡易インタビュー、③一次情報(独自アンケートやフィールドワーク)の3点を意識すると権威性を高められます。特に一次情報は他サイトとの差別化に直結します。たとえば、10人でもいいのでアンケートを取り、その結果をグラフ化して解説するだけで「自分で調べたオリジナルデータ」として価値が生まれます。インタビューはメール取材でも構いません。専門家に3つほど質問し、回答を引用すると記事全体の重みがぐっと増します。
用語補足(初心者向けミニ辞典)
| 用語 | かんたんな意味 |
| SEO | 検索で上位に表示されるようサイトを最適化すること |
| アルゴリズム | Google が検索順位を決める計算ルール |
| コアアップデート | Google が年数回行う大きな順位変動の更新 |
| SSL | ウェブページと閲覧者の通信を暗号化し、盗聴を防ぐ仕組み |
| CTR | 検索結果や広告がクリックされた割合(クリック率) |
公開前チェックリスト(5項目)
- 体験談・ビフォーアフターを入れたか?
- 資格・経歴をプロフィールに記載したか?
- 公的データや論文を引用したか?
- 運営者情報・連絡先を明示したか?
- 誤情報がないかファクトチェックしたか?
まとめ
E‑E‑A‑T は検索順位を左右する万能スイッチではありませんが、読者に長く愛されるメディアを育てるための“土台”となる考え方です。
今回紹介した「体験談を添える」「プロフィールを整える」「信頼ソースで裏付ける」「透明性を担保する」の4つをコツコツ実践すれば、Google アップデートの波にも強い記事が確実に増えていきます。
検索順位やクリック率が伸びるだけでなく「あの記事は分かりやすい」「また読みたい」とリピートされる好循環も生まれるでしょう。
まずはチェックリストを片手に、直近公開した記事を1本リライトしてみてください。

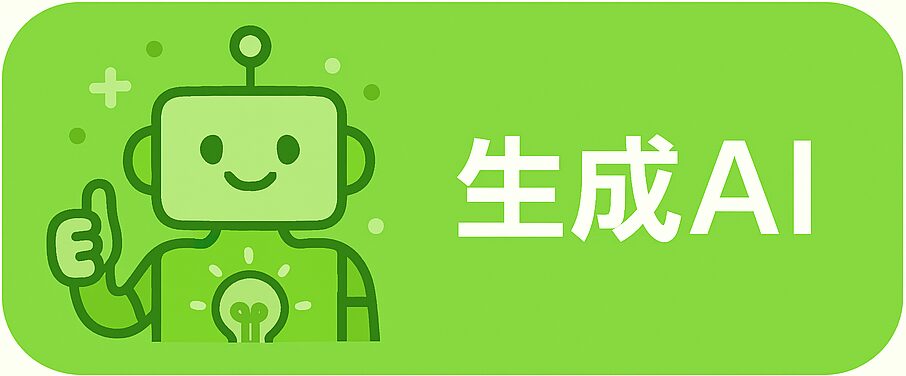
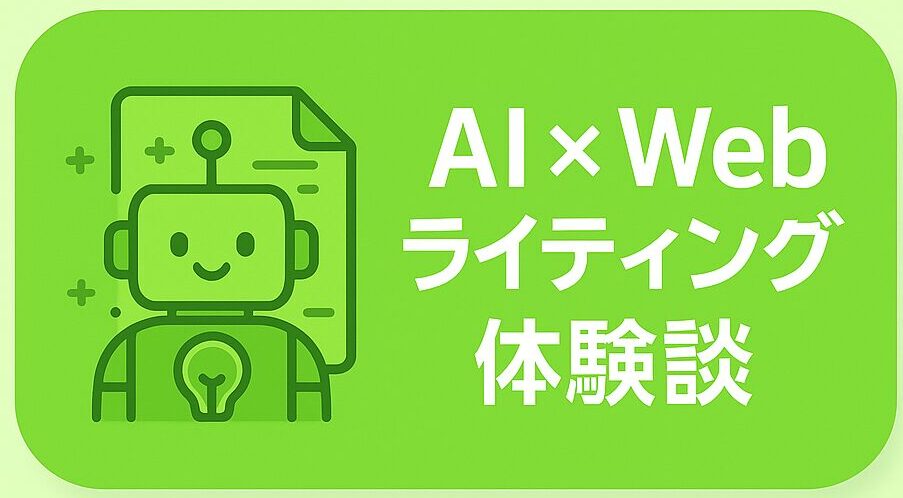






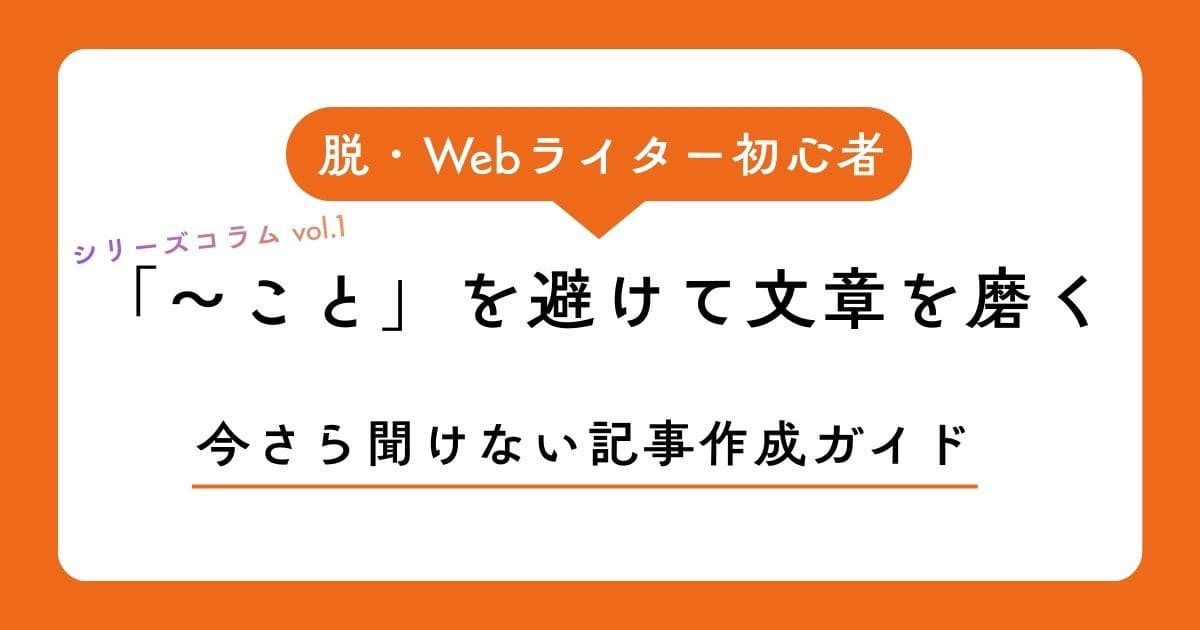
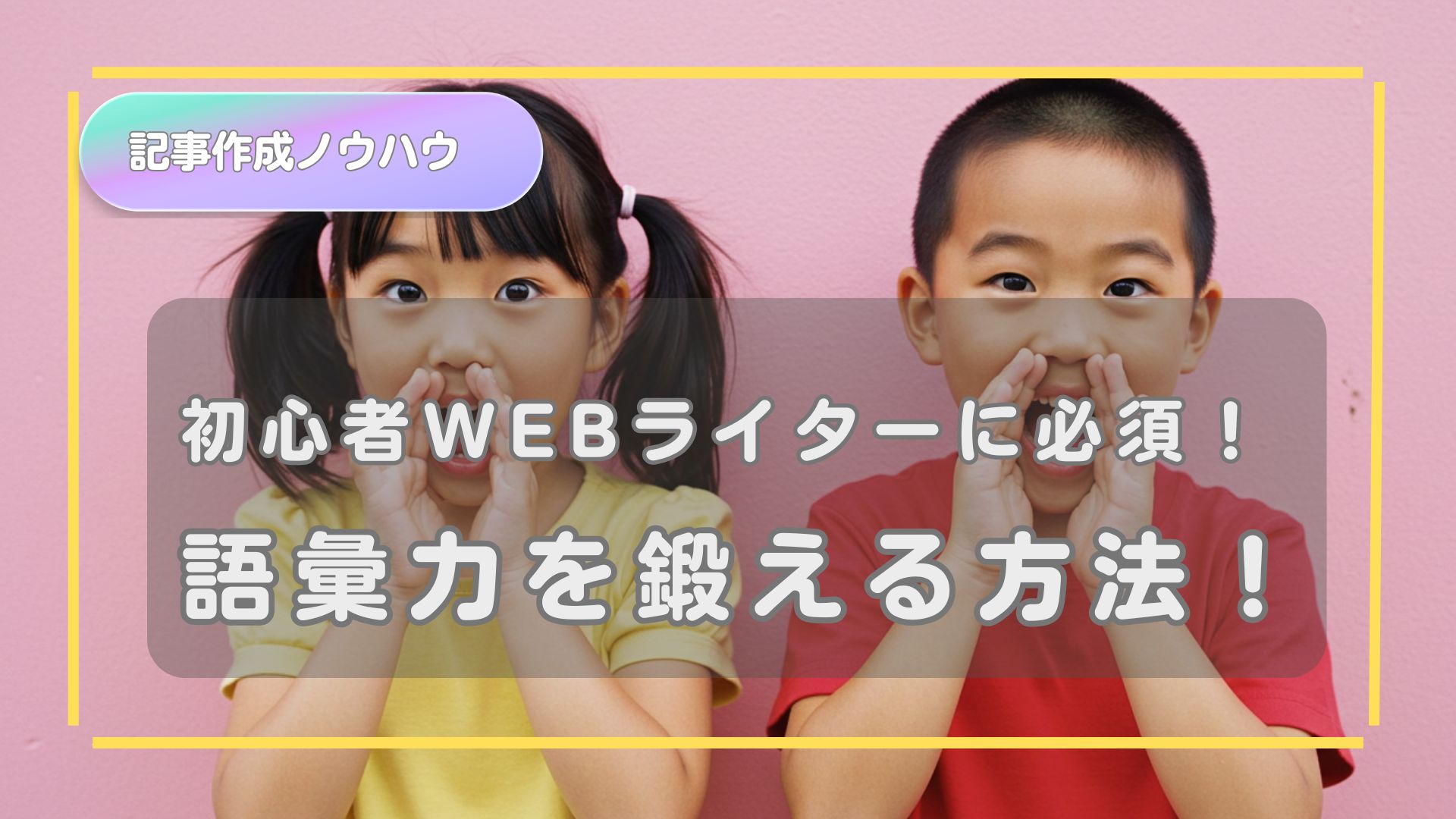

[…] E‑E‑A‑Tを高める基礎テクニックを以下にまとめているので、ぜひ読んでみてください。 […]
[…] Googleが高品質なコンテンツを評価するための基準として注目されているのが「E-E-A-T」です。検索意図を正確に捉えた上で、E-E-A-Tの観点を盛り込むことで、SEO的により強固なコンテンツを作ることができます。 […]