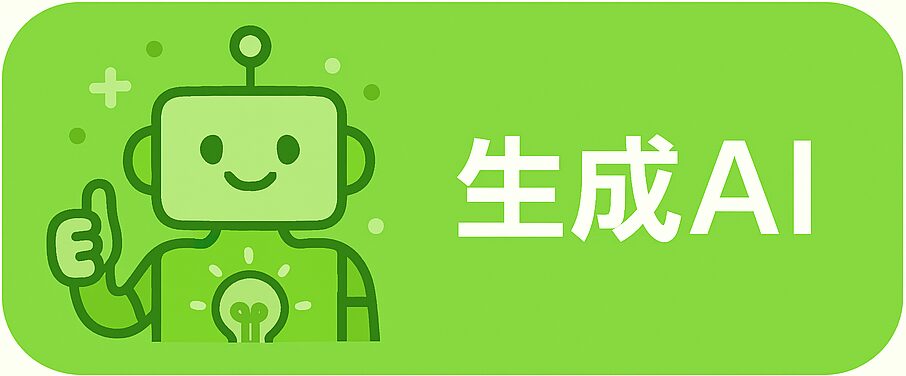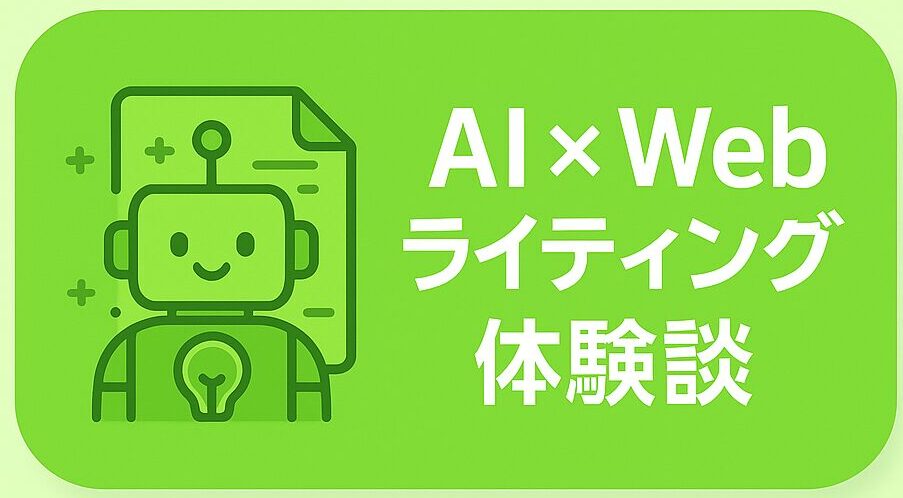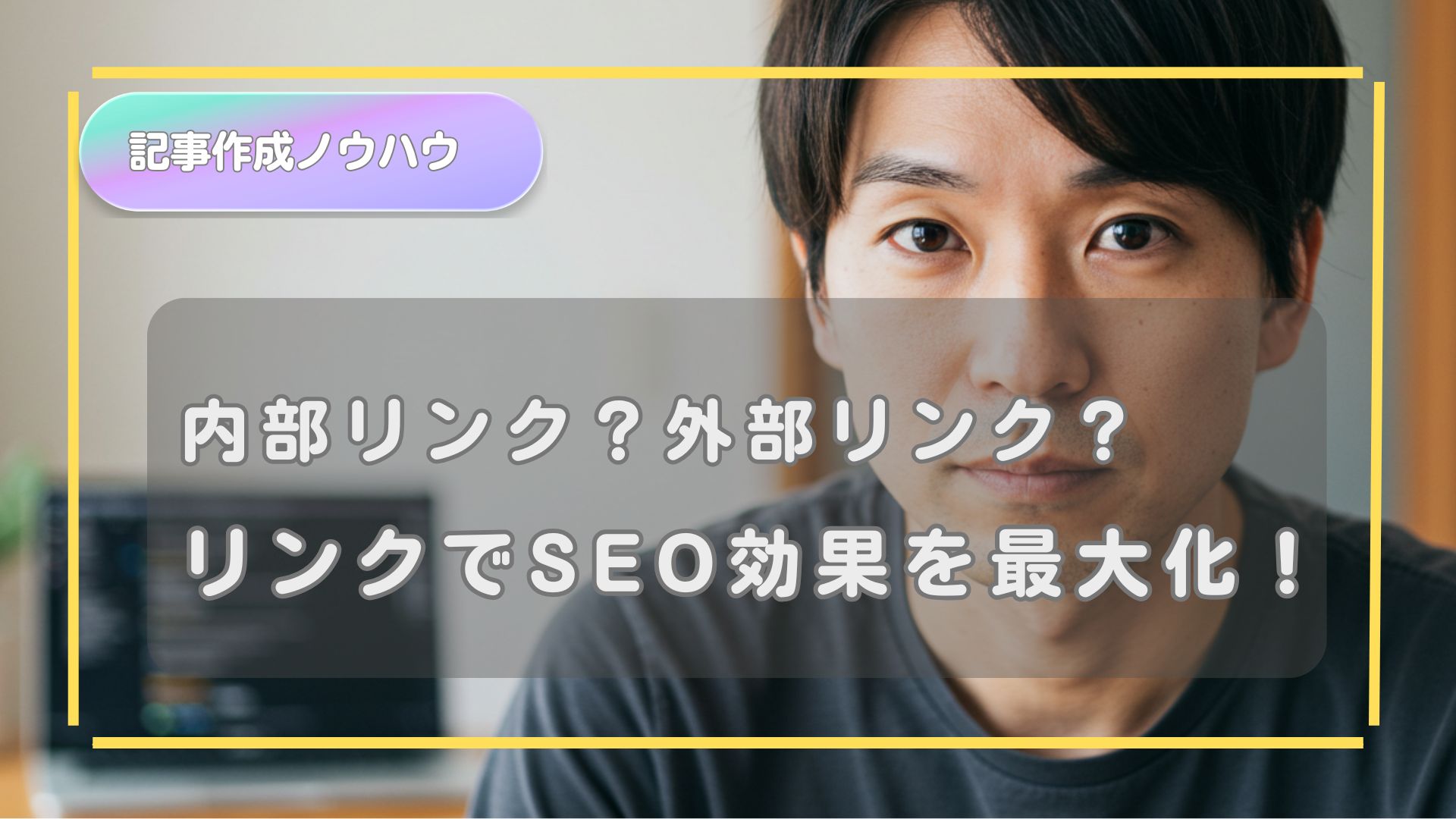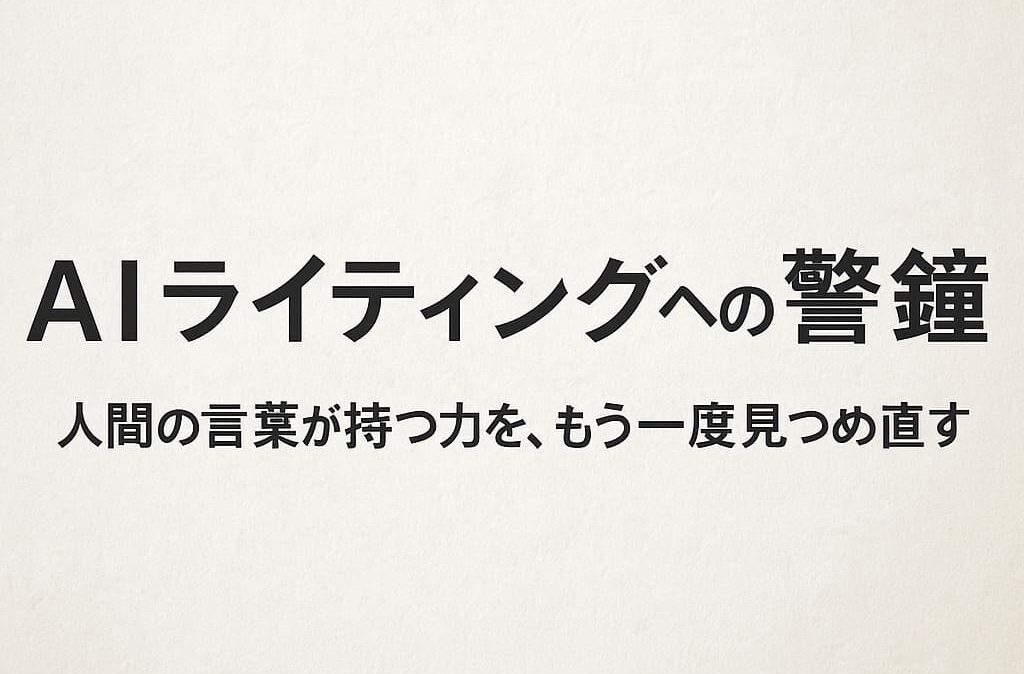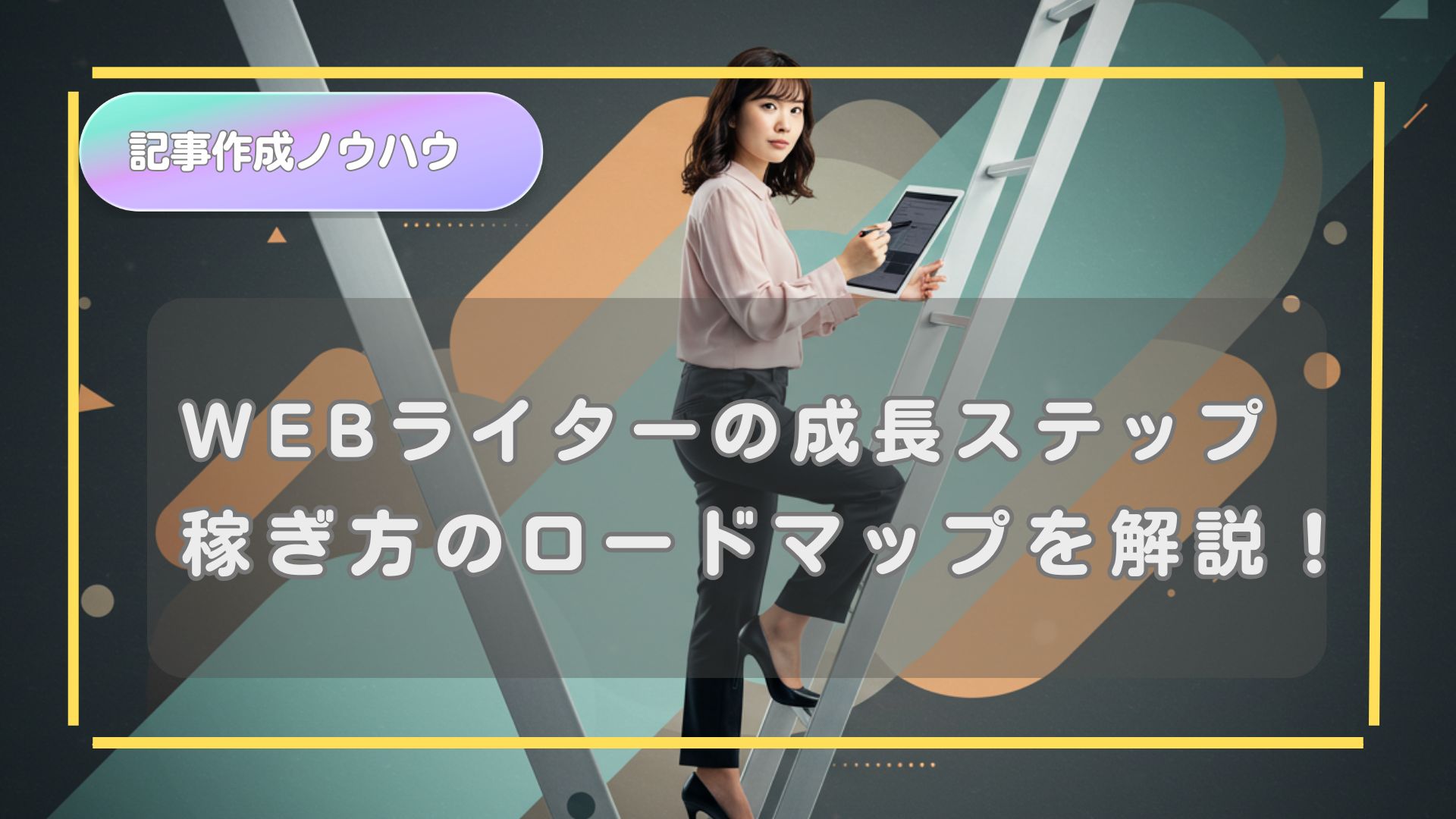結論のまとめ方!読者に行動してもらう締めくくりの書き方

「最後、どう締めればいいか分からない」――そんな悩みをこのページで解決しましょう。
こんにちは、加藤政則です。秋田県大仙市在住のWebライターとして2013年から活動しています。これまで、多くの読者を「読ませる」だけでなく「動かす」記事を追求してきました。
特に記事の締めくくりは、読者の行動を左右する重要なカギ。私自身も試行錯誤を重ねてきたからこそ、その効果を実感しています。
読者が記事を読み終えた瞬間、次に何をすべきかを示してくれるのが締めくくりです。
強いクロージングがあれば、読者の満足感が高まり、自らアクションを起こす後押しになります。
最後の数行だけで記事の印象がガラリと変わる――そんな魔法のような締め方のコツを、この記事で丁寧にお伝えします。
あなたの記事が「読まれるだけ」から「動かせる記事」へと変わる一歩を、さあ踏み出しましょう。
なぜ締めくくりが結果を左右するのか?

記事の締めくくりを工夫すると、読者が最後まで読んでくれたり、リンクをクリックしてくれたりする可能性がグッと上がります。
まずは、どれくらい変わるのか「イメージ例」をチェックしてみましょう。
| 何が変わった? | 変更前 | 変更後 |
|---|---|---|
| 最後まで読まれる人の割合 | 68% | 82% |
| ボタンを押す人の割合 | 0.9% | 3.4% |
たとえば、100人が記事を読むと、最初は68人しか最後まで到達しなかったのが、書き方を工夫すると82人に増えます。
同様に、リンクを押す人は元が1000人中9人だったのが、34人まで伸びるイメージです。
これはあくまで例ですが「締めくくりの工夫」がいかに大きな違いを生むかが伝わりますね。
ちなみに、変更前の68%は基本的に出来過ぎです。多くの読者は導入文と目次だけを見て離脱します。
記事を読み進めてもらうためには、導入部分や本文の書き方を工夫する必要になるので、ぜひ以下の記事も御覧ください。


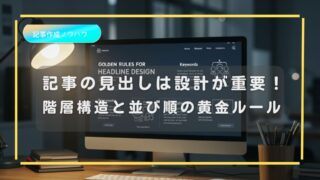


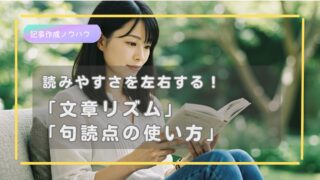
では、この先で具体的な5つのコツを見ていきましょう。
行動を引き出す5つのコツ
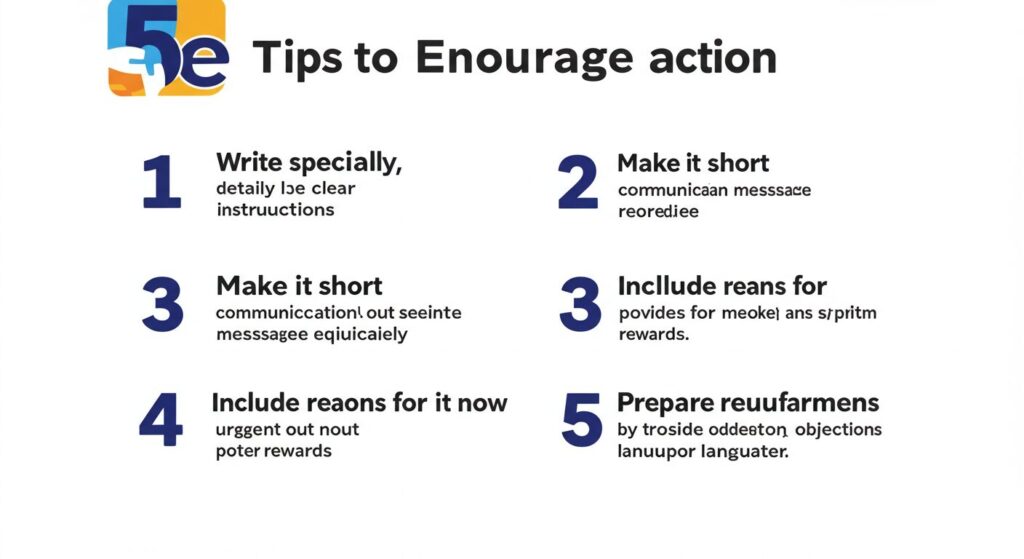
記事の最後で読者が「さっそく試してみよう」と思えるかどうかは、クロージングの仕方にかかっています。ここからは一つずつ深掘りしながら、具体的な書き方のポイントを解説していきます。
1. 具体的に書く
締めくくりで最初に大切なのは「何をすればいいのか」を明確に伝えることです。
たとえば「興味があれば確認してください」といった曖昧な表現では、読者は迷ってしまいがち。
そこで「まずは画面右上の『無料サンプルをダウンロード』ボタンをクリックしてみましょう」というように、ボタンの場所や操作手順まで示すと、読者は迷うことなく次のステップに進みやすくなります。
2. 短くまとめる
次に心がけたいのは、行動を促すフレーズの短さです。
人の注意力は短いため、長い文章は最後まで読まれずにスルーされる可能性があります。
理想は「〇〇はこちら→」のように10文字前後におさめること。
最小限の文字数で行動を示すことで、読者が一目で理解でき、即座にクリックしたくなる見た目にもつながります。
3. メリットを伝える
行動してもらうには「やってよかった」と感じられるメリットが必要です。
ただ「無料」と書くだけでなく、「無料サンプルを試すと、記事制作の時間が平均30%短縮します」のように、具体的な数字や効果を示すと説得力が増します。
自身の経験談や実績データを交えることで、読者は「自分にも同じ成果が得られるかも」と期待を抱きやすくなります。
4. 今やる理由を添える
読者は「いつでもできる」と思うと先延ばししがちです。
そこで、期限や数量の制限を付け加えると、行動の動機付けが強まります。
たとえば「先着200名様限定」「本日23:59まで○○円オフ」といった表現を使うと「今やらなきゃ」と思ってもらいやすくなります。
ここで重要なのは誠実さ。
実際の条件に基づく制限を示すことで信頼を損なわないようにしましょう。
5. 安心材料を用意する
最後に、読者の不安を取り除く言葉を添えて、クリックのハードルを下げます。
代表的なものとして「30日間返金保証」「利用者の声」「専門家の推薦コメント」などが挙げられます。
これらを短い一文で示すだけで、読者は「失敗しても大丈夫」と感じ、安心してアクションを起こしやすくなります。
5つの締めくくりテンプレート

ここからは、さまざまな場面に合わせて使える締めくくりの型を紹介します。初心者でも真似しやすい記事の締めくくりのテンプレートを用意しましたので、自分の記事に合わせてアレンジしてみてください。
① 3ステップ型(いちばん簡単)
「要約 → 共感 → 行動の提案」の流れで、読者の思考にそっと寄り添いながら締めくくります。
まず本文の要点をひとことでまとめ、次に「最初は慣れないかもしれませんが大丈夫」といった共感を挟んで安心感を与え、最後に具体的な行動を促します。
たとえば以下のように。
この記事で大切な3つのポイントはつかめましたね。
最初はぎこちなくて構いません。
まずは今日1本、この3ステップで締めくくってみましょう。
このように、自信を後押しする一言で締めると効果的です。
② PAS 型(問題 → 不安 → 解決策)
PAS 型とは、Problem(問題提示)・Agitation(不安の強調)・Solution(解決策)の頭文字をとった文章作成のテクニックです。
Problem(問題提示)で読者の悩みを再確認し、Agitation(不安の強調)で「放っておくとどう困るか」を具体的に描写します。
その後、Solution(解決策)として、自分の記事や商品に誘導し、行動のハードルを下げます。
PAS型の例文は以下のとおりです。
まだクロージングで悩んでいませんか?読者にアクションを促せないと、せっかく書いた記事が台無しになります。でも安心してください。この記事でご紹介した方法を使えば、最後の一行で大きく反応が変わります。
このようにすると、読者は「自分の問題を解決できそうだ」と感じられます。
③ BAB 型(現状 → 理想 → 行動の橋渡し)
BAB 型は、Before(現状)・After(理想)・Bridge(行動の橋渡し)の頭文字を取った文章作成のテクニックです。
Before(現状)の描写で読者が抱える課題を浮き彫りにし、After(理想)ではその課題が解消された未来をイメージさせます。
Bridge(行動の橋渡し)で具体的なステップを示して「理想へたどり着くために今何をすればいいか」を明確化します。
例文は以下のとおりです。
現状は、締めくくりが弱くて読者が去ってしまっているかもしれません。でも、強いクロージングができれば、読者が行動する記事に変えられます。まずは次のテンプレートを試してみてください。
④ Q&A 型
読者がよく抱く疑問を「質問 → 回答」の形式で解決し、そのまま行動ボタンへ誘導します。
FAQのように使うことで、読者は「自分の不安に答えてくれた」と感じ、安心してリンクをクリックできます。
また、複数の疑問を並べることで、検索エンジンにも評価されやすくなります。
例:
Q:どのテンプレートを使えばいいですか?
A:まずは3ステップ型から試してみるのがおすすめです。その後、PAS型やBAB型に挑戦して、効果を検証してみましょう。
→ テンプレート一覧を見る(リンク式のボタン)
⑤ ストーリー回収型
冒頭で触れたエピソードや印象的なフレーズを締めくくりで再登場させ、読者に「物語が完結した」満足感を与えます。
最初の問いかけや実例をもう一度振り返り「ここまで読んでいただき、ありがとうございました」と感謝を伝えたうえで、行動を促します。
たとえば、記事の冒頭で「私も最初は失敗ばかりでした」と書いたなら、最後に「私がこの方法で成功したように、あなたもきっと成果を感じられます。まずは一歩踏み出してみませんか?」いった具合です。
読者への呼びかけは心に響きやすいので、ぜひ取り入れてみてください。
行動を促す一言(例文集)
ここでは、読者に最後の一歩を踏み出してもらうための「短くて強力なフレーズ」を集めました。
例文をそのまま使うだけでなく、記事の内容や読者のニーズに合わせて言葉を入れ替えたり、順番を変えたりしてカスタマイズしてみてください。
ボタンテキストやリンク文言としても効果的です。
- 今すぐ無料で試す
- 資料を3秒でダウンロード
- 30日返金保証で安心スタート
- LINEで気軽に相談する
- 専門家に質問してみる
- 無料テンプレートを受け取る
- 1分でできる診断を始める
- 今だけクーポンをもらう
- 限定動画を見る
- 在庫がなくなる前にチェック
- 比較表を確認する
- ウェブセミナーに申し込む
- 実例集をメールで受け取る
- チャットで見積もり依頼
- 次の記事を読んで学ぶ
上の例文は、どれも「動詞で始め」「読者のメリットを含め」「なるべく短く」することを意識しています。
まずは自分の記事にピッタリの一文を選び、ベースとして活用してみましょう。
場面別の締めくくり例
まずは、記事のゴールに合わせて使える締めくくりの例を見てみましょう。以下の表から、自分の記事に近いシーンを選び、流れを参考にしてください。
| 場面 | 例文の流れ |
| 解説ブログ | 本文の要点を簡潔にまとめたあと「今日のポイントを1つ試してみませんか?」と問いかけ、関連記事へ誘導する |
| 商品紹介(アフィリエイト) | 商品のメリットを再提示してから「限定クーポン」を提示して「在庫がなくなる前にご確認ください」と呼びかける |
| ネット通販ページ | 実際の使用イメージを描写した後、ユーザーレビューを引用しつつ「カートに入れる」ボタンを強調する |
| 企業向け資料請求 | 費用対効果の試算結果を示し、成功事例を紹介したうえで「資料請求はこちら」へのリンクを設置する |
| メルマガ登録 | 登録するメリット(無料特典)を強調し、登録方法をシンプルに説明、最後に「個人情報は安全に管理します」と明記する |
これらは基本的な例です。
実際には、表現を足したり順番を変えたりして、読者が自然と次の行動へ進みたくなる文章にカスタマイズしてみてください。
次に、検索エンジンからも評価されやすい締めくくりのポイントを見ていきましょう。
Google に評価されやすい締めくくりの作り方

Google は検索品質評価ガイドラインの中で、記事の信頼度を測る指標として E‑E‑A‑T(経験・専門性・権威性・信頼性)を明記しています。
※参考:Search Quality Rater Guidelines: An Overview|Google
E‑E‑A‑T が高いページは、ユーザーの疑問に的確に答えられている「読者に役立つ記事」とGoogleから判断されやすくなります。
そして、ユーザーはしっかりと読んでくれるので、滞在時間やシェア、ブックマークなどの行動指標も伸びる可能性が高いです。
結果的に、サイト全体の評価向上につながり、検索結果でプラスの影響が出やすいという、一石二鳥のメリットがあります。
E‑E‑A‑T の概要は以下のとおりです。
経験(Experience)
書き手が実際に試した体験談や具体的なデータを示すことで「机上の空論ではない」ことを伝える役割を果たします。たとえば「この方法でクリック率が 20%上がりました」というように、数字を添えると説得力が増します。
専門性(Expertise)
その話題について深い知識があることを示す要素です。プロフィール欄に「Web ライター歴5年」「SEO 資格保有」などの情報を書いておくと、読者は「詳しい人が書いているのだ」と安心できます。
権威性(Authoritativeness)
外部の公的機関や研究機関、業界団体など、信頼できる情報源を引用して記事内容を裏付けることです。たとえば「総務省の最新統計によると〜」といった第三者データがあると、記事全体が客観性を帯びます。
信頼性(Trustworthiness)
運営者情報や問い合わせ窓口、プライバシーポリシーを明示し、「トラブル時に連絡が取れる」という安心感を与える取り組みです。これにより読者は不安を感じず、行動に移りやすくなります。
実際の SEO 施策でも、2024 年 3 月の Google コアアップデート以降、E‑E‑A‑T を高めたサイトが評価される傾向が強まっています。
記事の締めくくりに体験談・プロフィール・引用元・運営者情報を自然に盛り込み、E‑E‑A‑T をしっかり示すことで、検索順位の向上だけでなく、読者の信頼獲得にも直結します。
とはいえ、実際にそんなに簡単なものではありません。
E‑E‑A‑Tを高める基礎テクニックを以下にまとめているので、ぜひ読んでみてください。
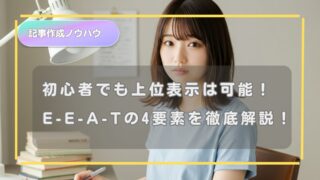
公開前のチェックリスト(10 項目)
- 要点を1文で言い切ったか
- 読者メリットが明確か
- 行動を促す一言が 18 文字以内か
- 今すぐやる理由を示したか
- 読者の不安を先回りして解消したか
- ボタンやリンクまで 1 クリックでたどり着けるか
- 同じ語尾が続いていないか
- 関連性の高い記事へ内部リンクを貼ったか
- 根拠となるデータや事例を入れたか
- 声に出して読んでリズムを確認したか
まとめ
締めくくりは、単なる「記事の出口」ではありません。
読者の心を動かし、次の行動へと導く「未来への入り口」です。
この記事で紹介した5つのテンプレートや5つのコツを参考に、まずは「3ステップ型」から、あなたの記事に試してみてください。
最初は戸惑うこともあるかもしれませんが、一歩踏み出すことで、読者の反応はきっと変わります。
行動して初めて、あなたの記事は真の価値を発揮します。
ぜひ今日から、読者の心に響く締めくくりで、あなたのメッセージを届けましょう。