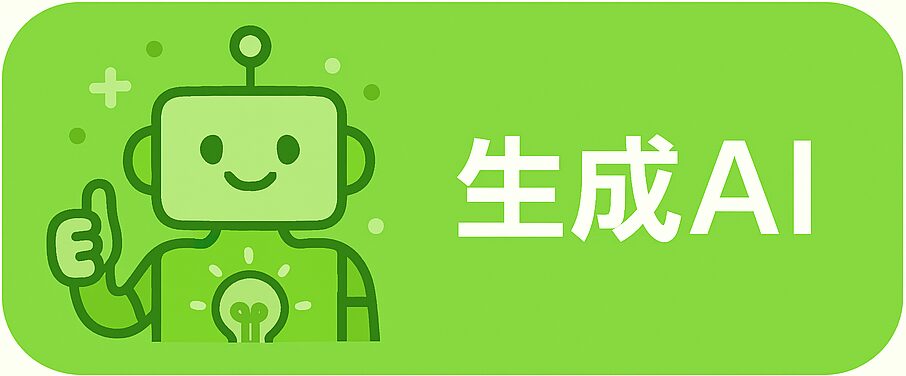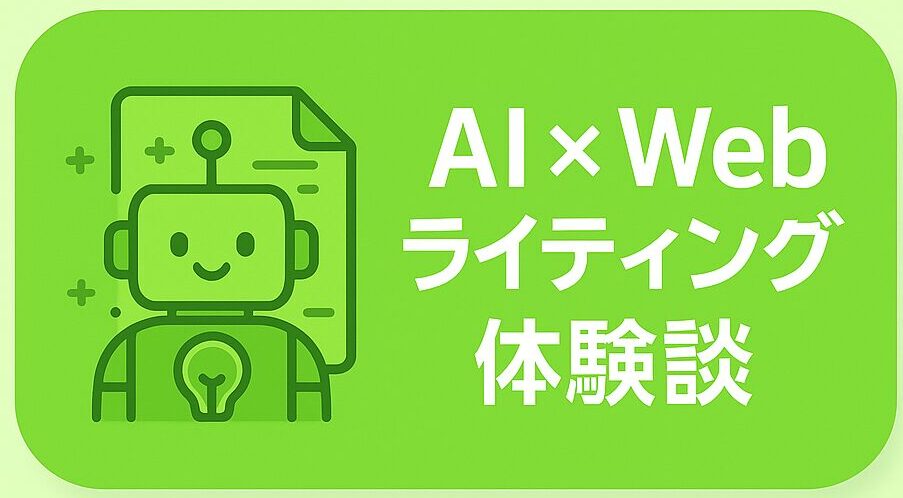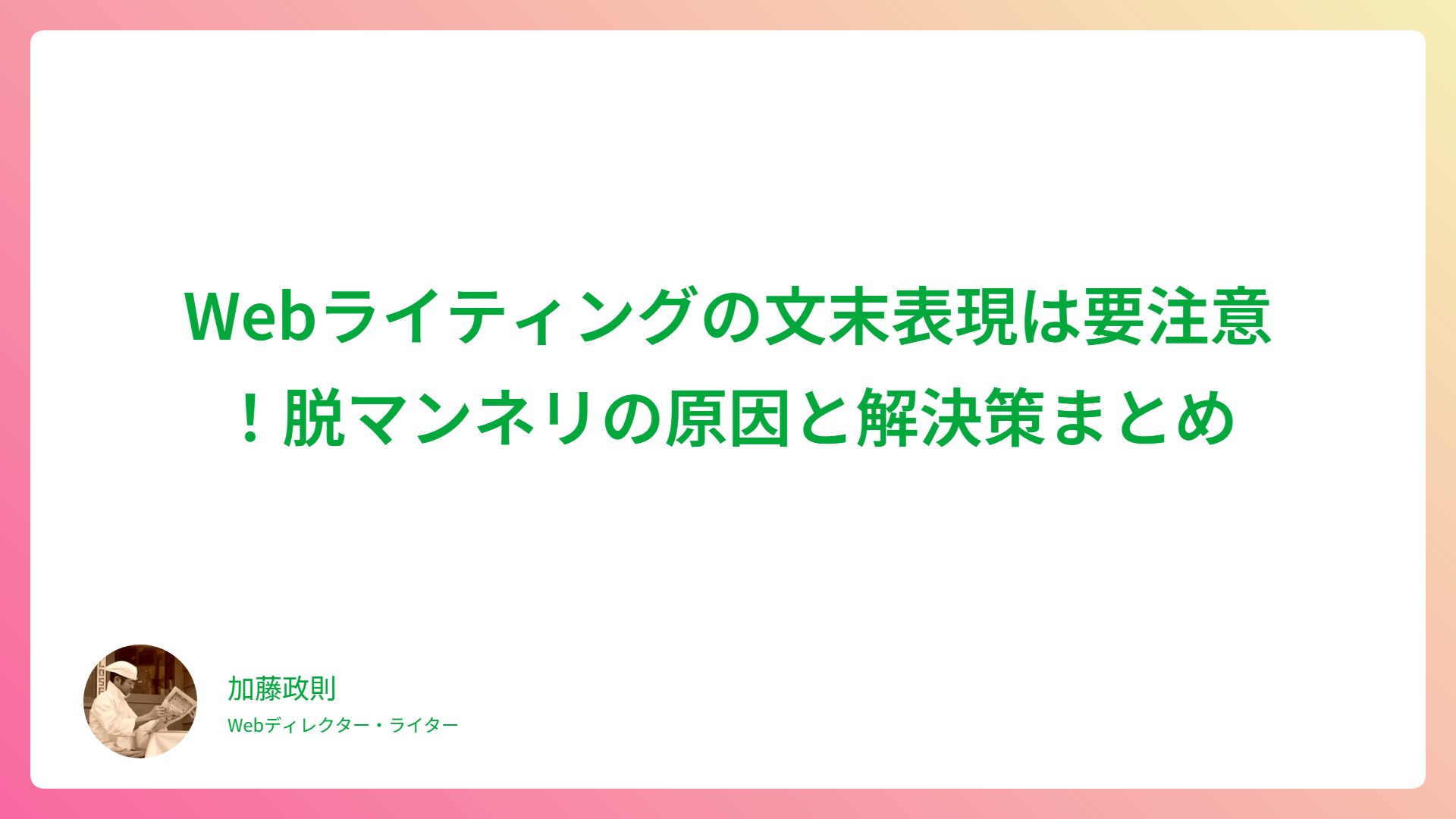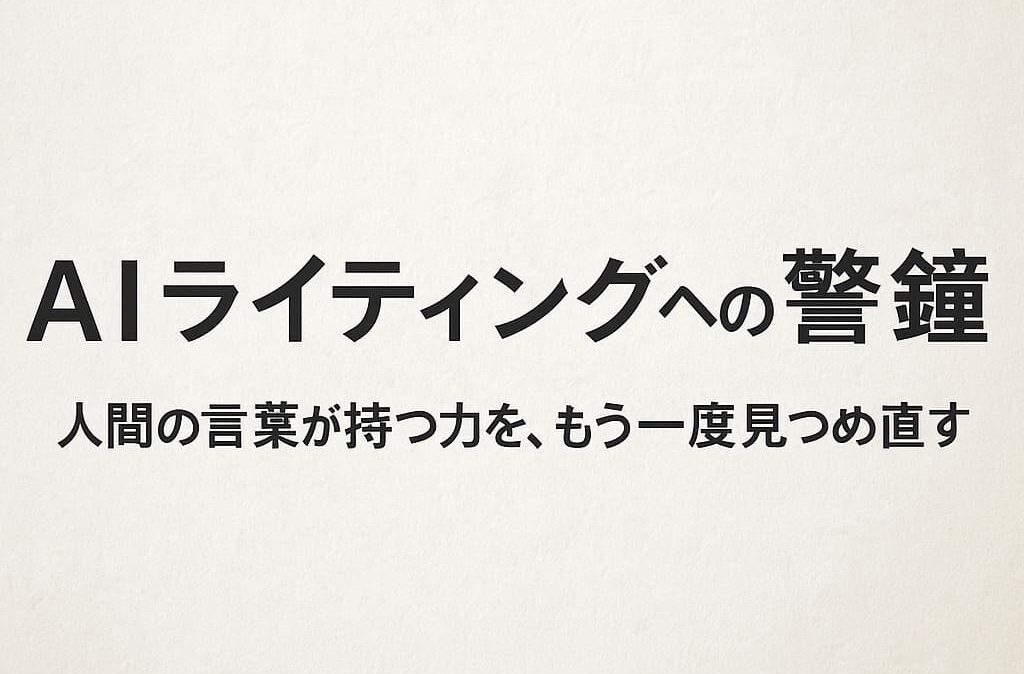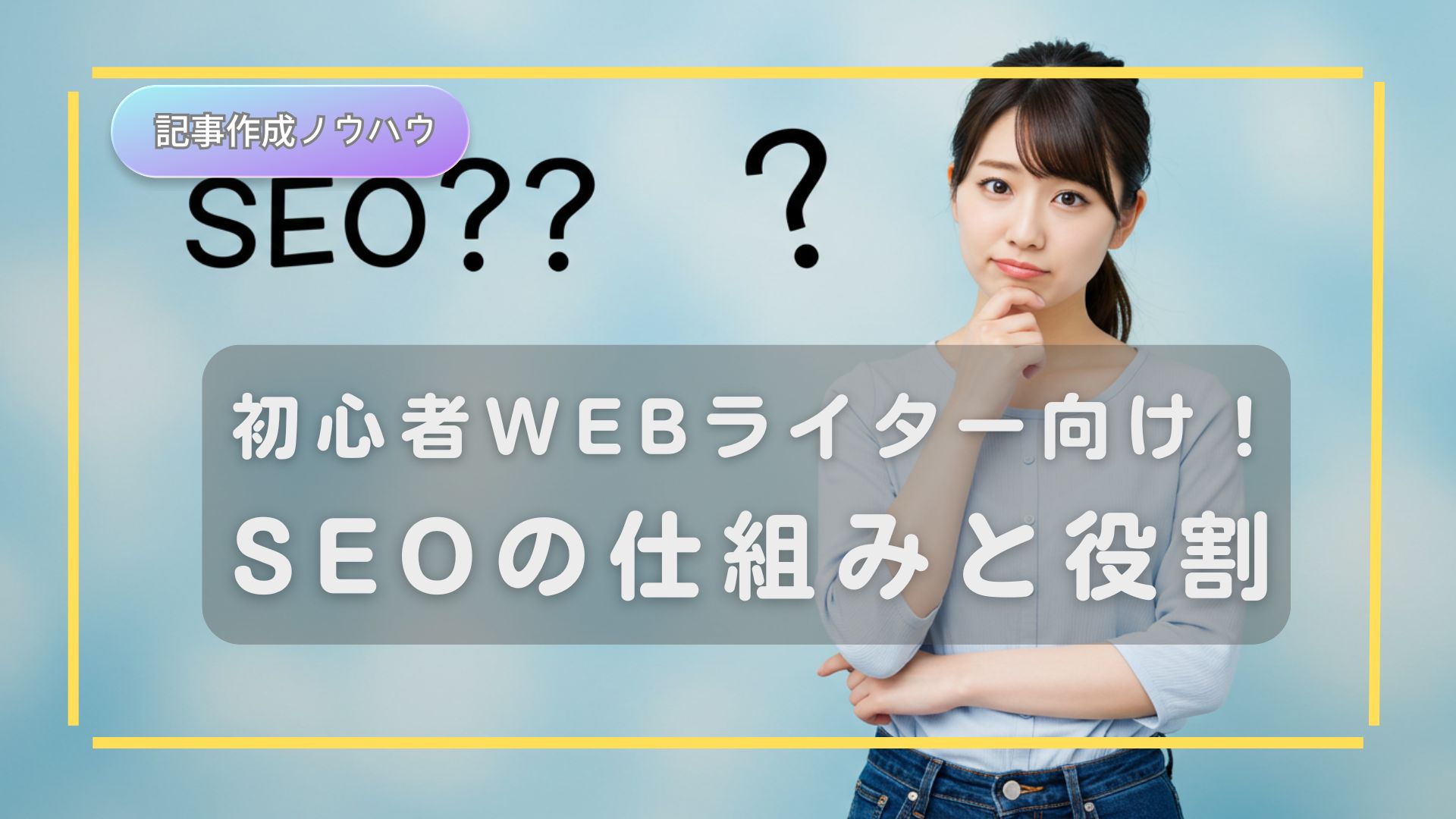専門用語は使わなくてOK!初心者ライターのための“分かりやすい言葉”選び完全ガイド

「え、そんなの知ってて当たり前でしょ?」
そう思って書いた文章が、読者にまったく伝わっていなかった…。そんな経験はありませんか?Webライター初心者の多くが直面するのが、“言葉の選び方”の難しさです。
特に、自分が詳しいジャンルで記事を書くとき、つい専門用語を多用してしまいがち。ところが読者の多くは、その言葉を初めて聞く人だったりします。
「分かりやすく書く」=「誰でも理解できるように書くこと」
この記事では、初心者でも今すぐ実践できる“分かりやすい言葉”選びの基本と、専門用語を噛み砕くテクニックを、豊富な例とともにご紹介します。
「分かりやすい文章」とは?読み手基準で考えよう
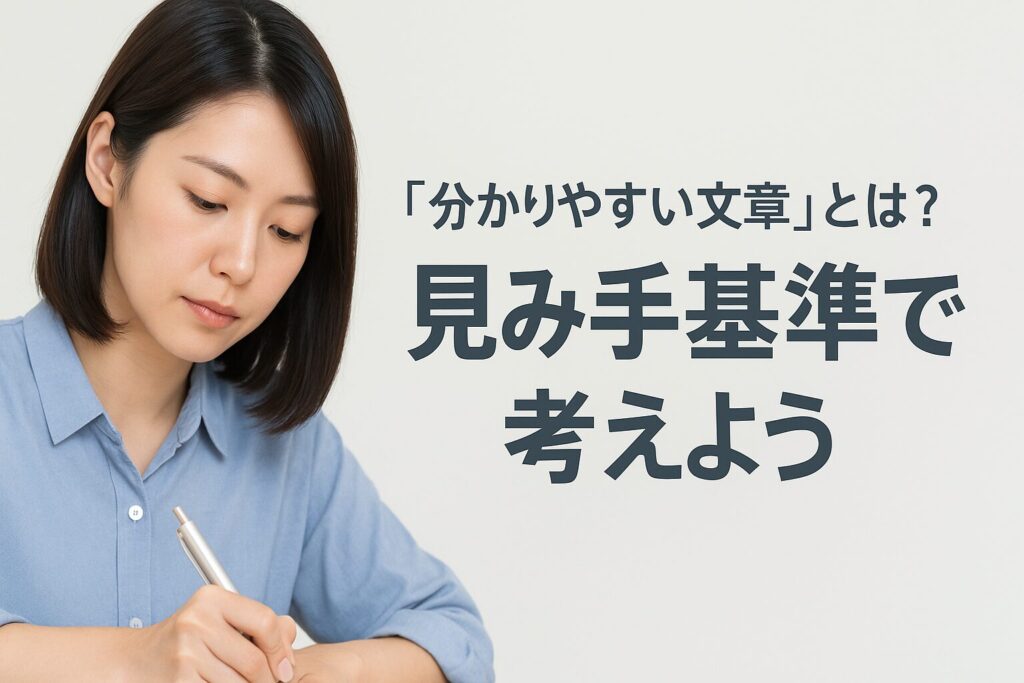
Webライティングにおける“分かりやすさ”は、書き手が感じるものではなく、読み手が感じるものです。どれだけ理路整然と文章が書かれていても、読者が「難しい」と感じたら、それは“分かりにくい文章”になってしまいます。つまり、分かりやすさの基準は常に読者側にあるのです。
専門家にありがちな“分かりにくい文章”
専門的な知識を持つ人ほど「これくらいは知っているだろう」と思い込みがちです。
しかし、Webライティングでは、初心者や一般の人が読む前提で文章を構成する必要があります。
たとえばこんな文章、見かけたことはありませんか?
「CTRの最適化には、CPCを抑えつつCVRを改善するLPO施策が有効です。」
マーケティング業界では当たり前の表現でも、読者によってはまるで暗号。これでは伝わるものも伝わりません。
では、どうすれば良いのでしょうか?次項から考えていきましょう!
専門用語を“やさしい言葉”に言い換える方法

「言い換え」とは、難しい言葉や専門的な表現を、誰にでも伝わる形に置き換えることです。ただし、ただの“言い直し”ではありません。「読者が理解しやすい形に変える」ことが目的です。ここでは、Webライティングにおける実践的な言い換え方法を3つの視点から解説します。
方法①:一言でなく、説明の“文”にする
短い専門用語を無理に簡単な言葉にしようとすると、かえって意味が曖昧になります。
そういうときは、言葉ではなく“文”で説明するのがコツです。
【専門用語】「LPO」
【言い換え】「Webページの構成やデザインを見直して、成約率を上げる取り組み」
より具体的に書くと、読者は言葉の意味を文脈の中で自然に理解できます。
このアプローチは「知らない言葉を聞いた瞬間に理解できない読者」に配慮したものです。
読者の時間を奪わずに、説明をワンステップで完了させられる点でも効果的です。
方法②:「たとえば」で具体的な場面を描写する
抽象的な言葉は、具体例を添えることでグッと分かりやすくなります。
【専門用語】「ユーザビリティが高いサイト」
【言い換え】「たとえば、初めて訪れた人でもすぐに目的のページが見つかるような、使いやすいサイト」
例え話や場面の描写は、専門知識のない読者との“共通の理解”を生む強力な手段です。
また、場面描写の導入により、読者が「自分ごと」として想像しやすくなる効果もあります。
方法③:「簡単に言うと〜」で前置きする
読み手に「これから説明しますよ」と構える時間を与えると、文章がスムーズに読まれやすくなります。
【専門用語】「ROIが悪化しています」
【言い換え】「簡単に言うと、かけたお金に見合う効果が出ていない状態です」
このような前置きは、読者の“理解の準備”を助ける有効な方法です。
特に、難しい概念や抽象的な指標に触れる際には、この一言があるかないかで読者の反応が大きく変わります。
この3つの方法は、単体でも効果的ですが、組み合わせて使うことでより強力な文章作成が可能です。
たとえば「簡単に言うと」で前置きし、その後に「たとえば」で具体例を挙げます。
そして最後に「〜という取り組みです」と文で締めくくることで、読者の頭の中に“言葉のイメージ”を立体的に届けられます。
ライティングは「書く」行為であると同時に「伝える」行為です。
専門用語をやさしく言い換える力は、単に読みやすい文章を作るためだけでなく、読者の信頼を勝ち取るためにも欠かせません。
読者の知識レベルに合わせた“目線調整”のコツ
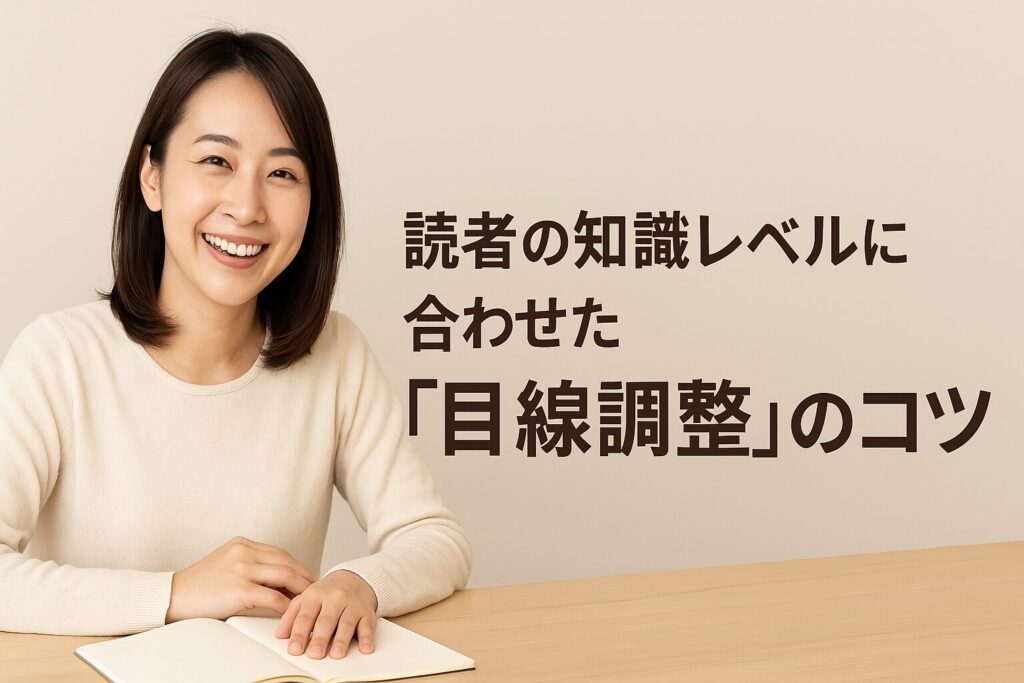
Webライティングで「伝わる文章」を書くために必要なのが、“読者との目線をそろえる”という視点です。書き手がどんな人に向けて書いているのかを明確に意識し、その読者が理解できるレベルに合わせて言葉を選びましょう。
知識ギャップを意識する
あなたが当たり前に知っている用語でも、読者にとっては初耳かもしれません。たとえば、以下のような違いがあるとします。
- ライター目線の想定読者:広告業界の経験者
- 実際の読者層:初めて副業でライターを始めた主婦や学生
このギャップがあると、内容が伝わらず、途中で読むのをやめられてしまうリスクがあります。
では、想定読者のズレが起きるのでしょうか?
多くの場合、ライターは自分の関心や知識に集中してしまい、読者との違いを意識しなくなります。
特に、自分が慣れ親しんだ業界や分野では、説明不要だと錯覚してしまうのです。
しかし、Web記事の読者層は非常に広く、経験や知識に大きなばらつきがあります。
だからこそ「これは読者に伝わるか?」という視点を常に持つことが必要です。
たとえば「LP」という用語を使う場合、「ランディングページの略称で、商品の購入や問い合わせにつなげる専用のWebページ」と、段階的に説明すると理解が深まります。
専門用語を避けるのではなく、補足説明と具体例で“翻訳”することがポイントです。
ペルソナを思い浮かべる
記事を書くときは、読者像(ペルソナ)を1人に絞って考えると、自然と目線が整います。
たとえば以下のように。
30代女性。小学生の子どもを育てながら、Webライターの仕事に挑戦中。マーケティング用語にはあまり詳しくないが、文章を書くのは好き。
このように具体的に想定することで「この言葉は難しいかな?」「もっと具体的に説明したほうがいいかも」といった判断がしやすくなります。
読者がつまずくポイントを先回りして拾う
読者との目線を合わせることは、やさしい文章を書く以上に、“読者がどこで疑問を持ちそうか”を予測する力です。
「この単語は何?」
「何がポイントなの?」
「どう役に立つの?」
といった疑問が生まれる場面を先読みし、あらかじめ答えておく。その姿勢が「この文章は親切だ」「分かりやすい」と感じてもらえる鍵になります。
多くの初心者ライターがやりがちな失敗は「これくらい分かっているはず」と思って説明を省いてしまうことです。
専門用語だけでなく、背景知識や手順も“前提なく丁寧に”伝えることが、信頼を得る文章につながります。
説明しすぎて損することはありません。
むしろ、読者から「丁寧で親切」と思われるほうが、記事としての価値は高まります。
書き手が無意識に使ってしまう“難しい言い回し”の見直しポイント
Webライティングの初心者、経験者にかかわらず「難しい言葉を使っているつもりはないのに、読みにくいと言われる」という経験は少なくありません。これは多くの場合、“日常ではあまり使わない言い回し”や“回りくどい表現”が原因です。ここでは、知らず知らずのうちに使ってしまいがちな難解表現と、分かりやすい表方法を解説します。
よくある“堅い言い回し”と改善例
| 難しい表現 | 分かりやすい表現 |
|---|---|
| 〜において | 〜で、〜の中で |
| 〜することが可能です | 〜できます |
| 〜に該当する | 〜に当てはまる |
| ご理解いただけますと幸いです | 分かってもらえたらうれしいです |
| 検討を重ねた結果 | 何度も考えた末に |
こうした表現は、ビジネス文書や論文にはよく使われますが、Web記事では不自然になりやすく、読者に「堅苦しい」「よく分からない」という印象を与えてしまいます。
ただし、記事のタイプや想定読者によっては難しい表現にした方が良い場合もあるので使い分けが重要です。
私もできていないケースが多々あるので、お互いに気をつけましょうね。
書いたあとに“声に出して読む”習慣を
文章を書き終えたら、自分の書いたものを音読してみましょう。
「口に出すと不自然だな」と感じた部分は、言い回しが固くなっている証拠です。
Webライティングでは「優しく親しみやすい文体」が読者に好まれます。
読者が“スムーズに理解できる”状態を目指していきましょう。
言い換え力を鍛える!初心者におすすめのトレーニング法
「この言葉、どう言い換えたら分かりやすいんだろう…」
そんな場面で立ち止まってしまうのは、ライターとして自然なことです。しかし、繰り返し練習することで“言い換え力”は確実に身につきます。ここでは、初心者でも取り組みやすく、分かりやすい言葉選びができる、実践的な「言い換え力」を身につけるトレーニング方法を紹介します。
トレーニング①:専門記事をやさしく書き直してみる
初心者ライターにとって、効果的な練習のひとつが「難解な文章を中学生にも伝わるようにリライトする」方法です。
これは、単なる文章の書き直しではなく「読者視点で言葉を選ぶ力」「要点を絞る力」「比喩や例えを活用する力」を総合的に鍛えるトレーニングです。
STEP1:1文ずつ区切って“何を伝えたいか”を把握する
まずは、原文を細かく区切りながら読んでいきます。
そして、各文の中にある「主張」「理由」「例」「背景」などを分類して書き出します。
たとえば以下のとおりです。
原文:イノベーションとは、技術・製品・サービスにおいて、従来の常識を覆すような新たな価値を創造する取り組みを指す。
→ 主張:「イノベーションとは、新しい価値を生み出すこと」
→ 背景:「今までの常識を壊すような技術やサービスが対象」
この作業で「何を言おうとしているか」が見えてきます。
STEP2:難しい単語をリストアップする
次に、その文章の中で「小学生や中学生には理解が難しいかも」と思われる言葉をピックアップします。
- イノベーション
- 常識を覆す
- 価値を創造する
- 取り組み
このように、使い慣れた言葉でも、相手の立場に立つと難解に感じる場合があることに気づけるのも、この練習のメリットです。
STEP3:やさしい日本語やたとえ話で言い換える
最後に、リストアップした難解語を、より身近な言葉や例えを使って書き換えます。
「伝える相手が中学生である」と仮定すると、言葉の選び方が変わります。
- イノベーション → 今までになかった新しいやり方
- 常識を覆す → 当たり前と思っていたことを変える
- 価値を創造する → みんなが「すごい」と思うようなことを生み出す
- 取り組み → やり方・努力
これらを使って書き直すと、次のようになります。
イノベーションとは、今までの当たり前を変えて、みんなが“便利”とか“すごい”と思うような新しいやり方を考えて実行することです。
文の構成はほぼ同じでも、読者にとっての“伝わりやすさ”が大きく変わるのが実感できるでしょう。
補足:この練習の応用先は無限大
このトレーニングは、SEO記事・商品説明・企画書・インタビュー記事など、あらゆるジャンルに応用可能です。
特に「業界知識が必要な案件」や「幅広い年齢層が読むコンテンツ」では非常に重宝されます。
しかも、オリジナルの表現になり、他人のコピー記事になりにくい点もメリットです。
プロのライターでも、初めての分野に取り組むときはこの“書き換えトレーニング”を行っていることがあります。
それほど基本でありながら、効果の高い方法です。
トレーニング②:「これは何?」ゲームを日常に取り入れる
日々の生活のなかに「これはどういう意味?」「簡単に言うと?」という問いかけを取り入れるのが、このトレーニングの本質です。
頭の中でゲームのように繰り返すことで、自然と“やさしい言葉で説明する力”が身につきます。
たとえば、電車内の広告、テレビのニュース、SNSの投稿、企業のプレスリリースなど、身の回りには“難解な言葉”が溢れています。
これらを見つけたら、ゲーム感覚で以下のように置き換えてみましょう。
- DX(デジタルトランスフォーメーション)→デジタル技術で、会社のやり方を便利に変えること
- エンゲージメント → 人とのつながりや信頼感
- コンバージョン → 目的としていた行動をユーザーがしてくれたこと(商品購入や申込みなど)
このように“翻訳”を日常に組み込むことは、単なる語彙の置き換えではありません。
難しい言葉の背後にある「背景」や「目的」をつかみ、それを読者に伝わるように再構築する作業です。
さらに効果的な方法として、“答え合わせ”をしてみることもおすすめです。
これを繰り返すうちに、“伝えること”に必要な知識と想像力が養われていきます。
また、書き出した言い換えフレーズは、ノートやアプリに保存して自分だけの「読者向け表現集」として活用するのもおすすめです。
トレーニング③:他人の記事の言葉遣いを観察する
人気Webメディアやnote、企業ブログなどには、数多くの“伝わる言い回し”や“難しい言葉のやさしい翻訳”が散りばめられています。
これらを「なんとなく読む」のではなく、意識的に観察することで、言葉選びの感覚が磨かれていきます。
たとえば以下のような視点で読み進めてみてください。
- 難しい概念をどうやって言い換えている?
- たとえ話や比喩はどんな種類のものが使われている?
- 同じ意味を持つ言葉の中で、なぜその単語を選んでいる?
“なぜそう書いたのか”を逆算して考える
「なんでこの表現を選んだんだろう?」という視点で考えると、書き手の意図や読者への配慮が見えてきます。たとえば:
- 「デジタル・ディバイド」という難しい言葉を、「ネット環境の違いで、できることが限られる状態」と言い換えていた
- 「パラダイムシフト」を、「当たり前がガラリと変わること」と説明していた
このように、“意訳”や“意図的な咀嚼”を意識的に吸収する姿勢が大切です。
ストック法:あなただけの「言い換え辞書」を作る
観察して気になった表現は、すぐにノートやスプレッドシートに記録しましょう。
「難しい言葉 → やさしい言葉」「抽象 → 具体」といった対照表のような形で残しておくと、執筆時に活用しやすくなります。
| 難しい表現 | 言い換え例 | 備考・どこで見たか |
|---|---|---|
| アセット | 資産・資源 | ○○社ブログ |
| サステナブル | 長く続けられる、持続可能な | note記事「〜」 |
| イノベーション | 新しい技術や仕組み | ○○Webマガジン |
この「自分専用辞書」は、書けば書くほど増えていきます。
まさに“現場で使えるツール”として、ライターの力を底上げしてくれる武器になるでしょう。
まとめ:わかりやすい言葉選びは、読者への“やさしさ”
Webライティングをするなかで、専門用語や難しい表現を使わないことは、“手抜き”ではなく“配慮”です。
文章を書くということは、読み手に寄り添うこと。
相手の知識量や読みやすさを想像しながら、丁寧に言葉を選ぶことが、信頼と共感につながります。
読者は「すごい文章」よりも「分かりやすく伝わる文章」を求めています。
難しい言葉を使えば“それっぽく”見えるかもしれませんが、それで伝わらなければ意味がありません。
まずは「中学生でも理解できるか?」という視点で、言葉を見直してみましょう。