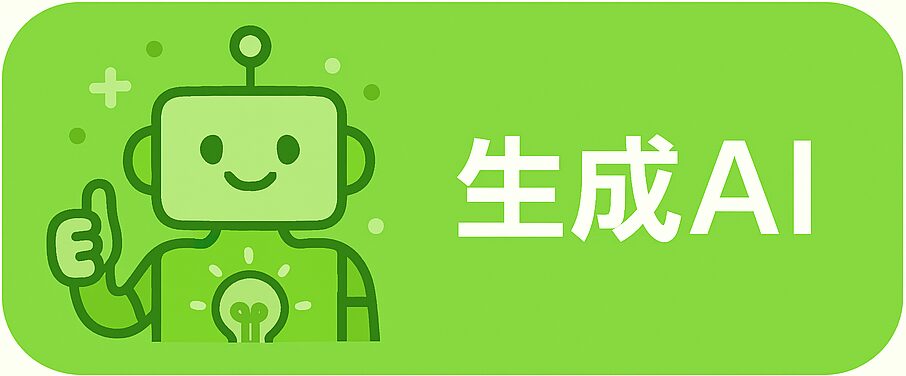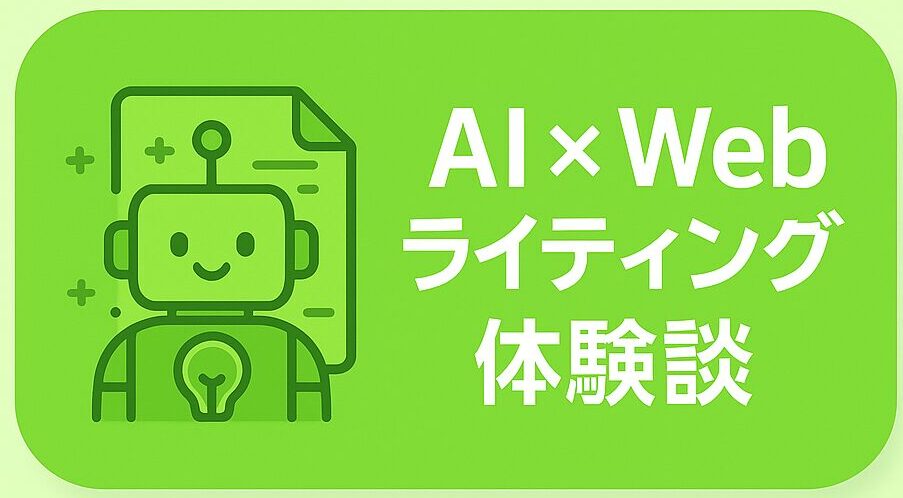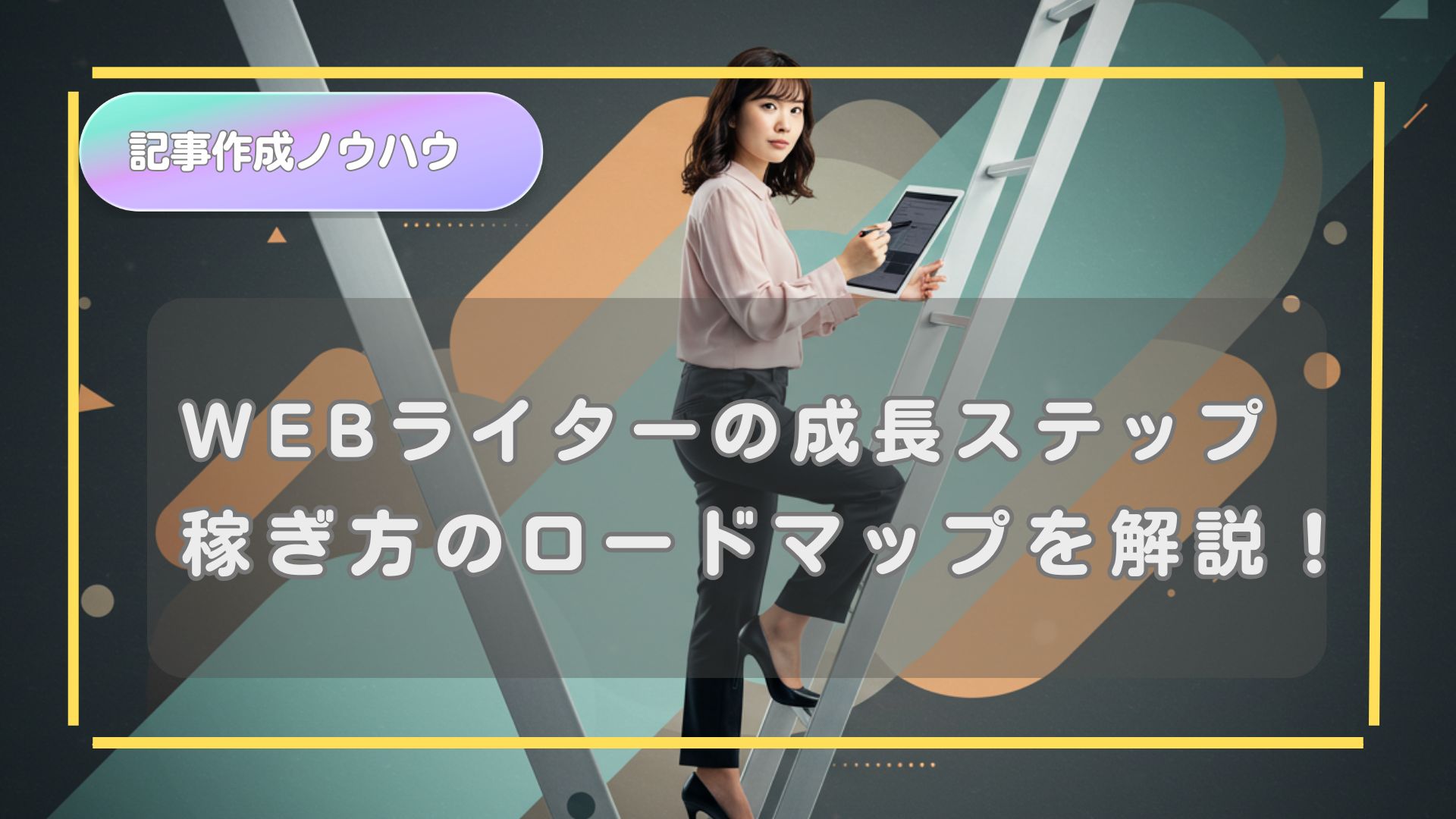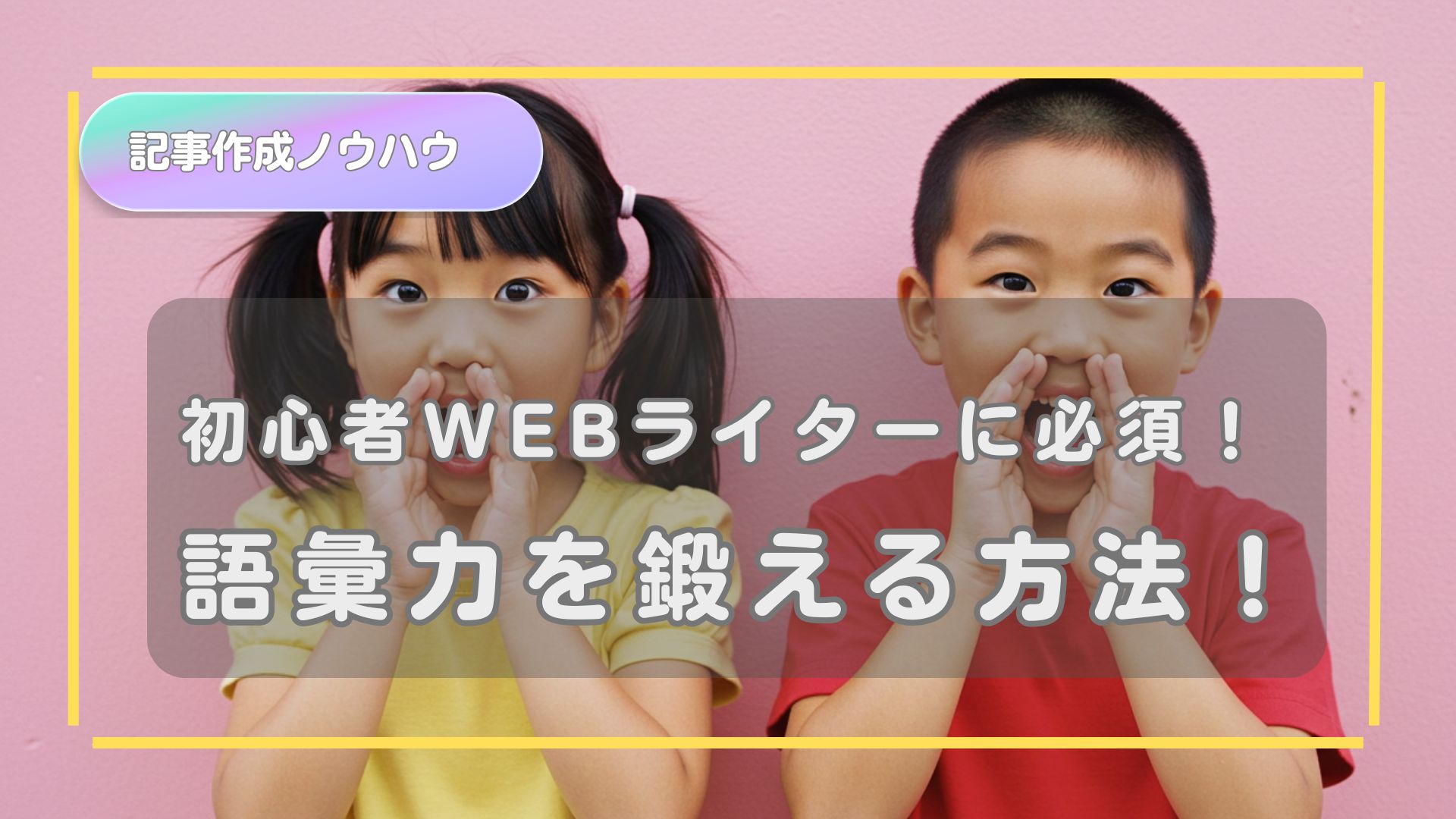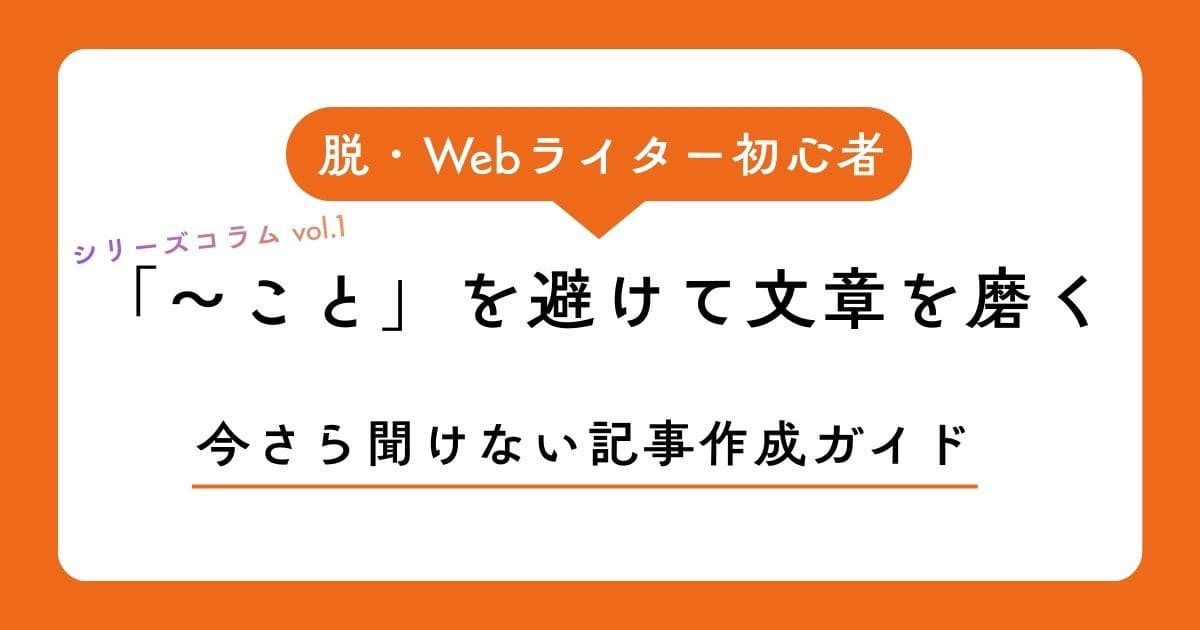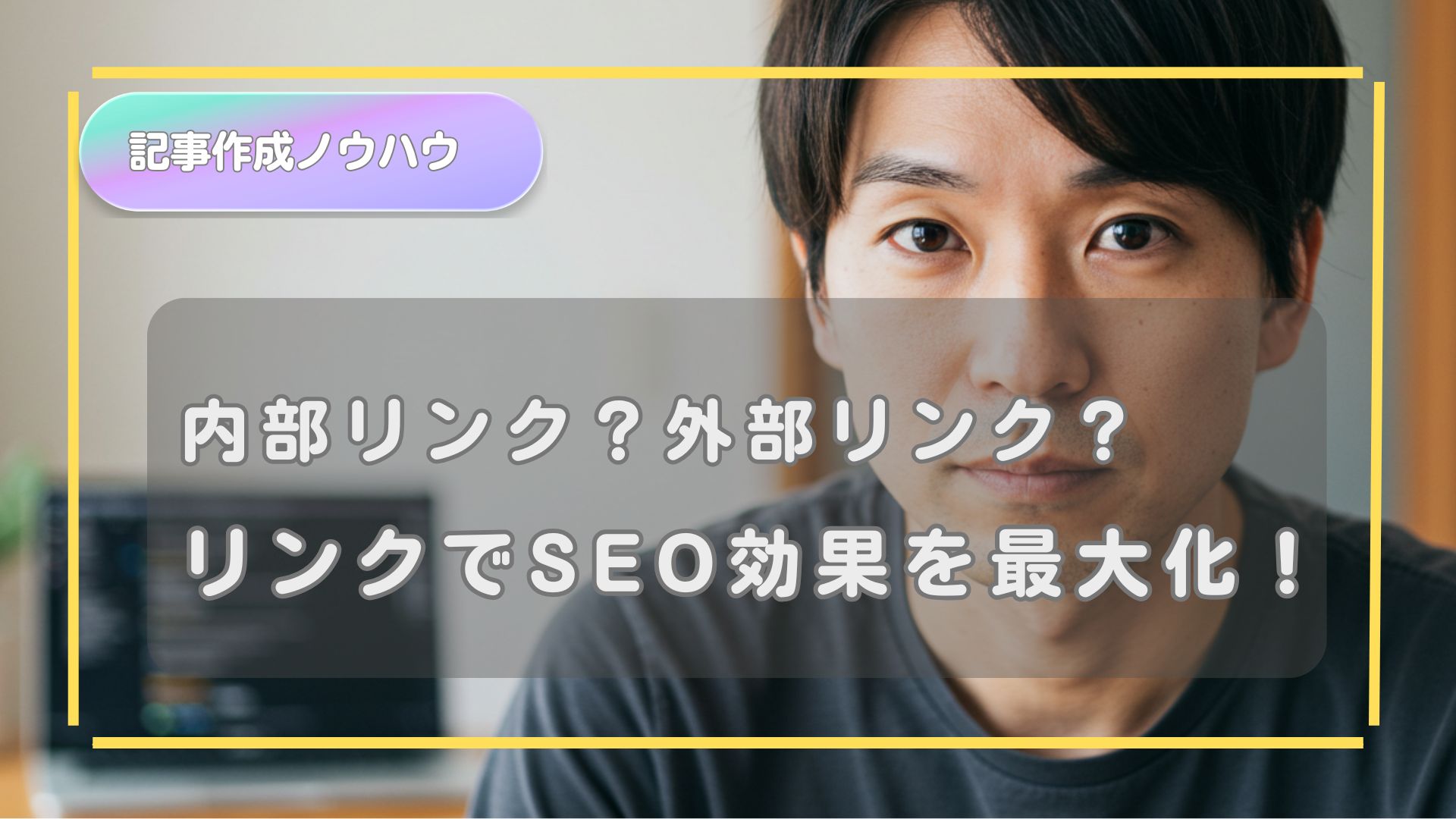説得力ある本文を書くための基本構成術!初心者Webライターの実践ガイド

Webライティングの本文で最も重要なのは、読者に「納得感」を与えることです。
ただ事実や報を並べるだけでは、読者の信頼や共感は得られません。
記事の本文では「主張→根拠→具体例」の3段階を意識することで、文章に筋道が通り、説得力が格段に高まります。
この記事では、初心者でも再現できる「説得力のある本文構成術」を、ステップ形式で分かりやすく解説します。
本文の目的とは?
本文では、読者の悩みや疑問に答え、納得感のある解決策を提示することが求められます。そのために、どのような役割を持ち、どう構成すれば良いのかを理解することが重要です。本文の主な役割は以下の3つです。
1. 記事全体の主張や目的を明確に伝える
記事の方向性を冒頭だけでなく各セクションでも明確にし、読者が「今何を読んでいるのか」が常に分かるようにします。明確で分かりやすい文章は、読者の安心感を高め、読み進めてもらえる可能性が高くなります。
2. 読者の疑問や悩みに“納得できる答え”を提示する
単に情報を並べるのではなく、読者が知りたい物事に対して、筋道を立てた論理と信頼できる根拠、そして具体例を用いて解答していきます。「なるほど、そういうことだったのか」と思わせることで、記事への信頼が生まれます。
3. 読後の行動(理解・実践・共有)につなげる
読者は知識を得るだけでなく、それを使って「行動」したいと思っています。本文では、その行動に直結するヒントや次のステップをさりげなく示すことで、記事の実用性がぐっと高まります。さらに共有されることで、記事の拡散や認知度向上にもつながります。
この3つを満たすことで、読者にとって「読む価値のある記事」となり、ライターとしての信頼も自然と積み重なっていきます。
本文構成の基本「PREP法」を応用する
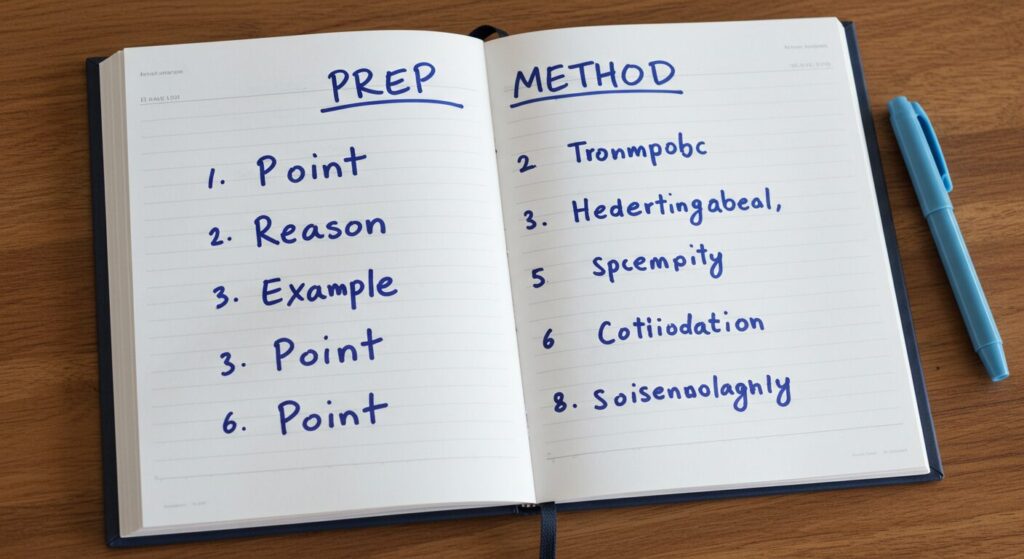
Webライター初心者にとって使いやすい構成法のひとつが「PREP法」です。
PREP法は、読み手の理解を促しながら、論理的な流れで主張を展開するのに最適な型で、以下の4つの要素で構成されています。
PREP法の構成要素
P(Point)=結論・主張
最初に、伝えたい結論を端的に示します。読者は何について書かれているかを即座に把握できます。
R(Reason)=理由・根拠
次に、結論に至る理由を明確に示します。読者に「なぜそう言えるのか?」という問いに対する答えを提供する部分です。
E(Example)=具体例・データ
ここで、実際の事例やデータなどを使って根拠を裏付けます。抽象的な主張だけでは信頼されにくいため、説得力を補強する要素として欠かせません。
P(Point)=まとめ・再主張
最後に、あらためて主張を簡潔に繰り返し、読者の理解と記憶に残るようにします。
この順番で書くことで、読者が内容をスムーズに理解しやすくなり、自然と説得力も高まります。
PREP法を用いた本文構成例
「記事は短く区切ったほうがよい(Point)」。
なぜなら、スマホで読む読者は長文だとストレスを感じやすく、離脱しやすくなるからです(Reason)。
たとえば、1文が5行以上続く記事より、2〜3行で改行された記事のほうが読了率が高いというデータもあります(Example)。
したがって、記事を書くときは「1文1思考」を意識し、読みやすさを優先しましょう(Point)。
PREP法は、構成がシンプルで再現性も高いため、初心者ライターにとって特におすすめです。
説得力のある文章を書く第一歩として、まずはこの型をベースに練習してみましょう。
初心者が陥りやすい3つのミスと改善策

PREP法を使えば説得力のある構成が可能ですが、初心者のうちは思わぬ落とし穴にはまることもあります。ここでは、特に多い3つの失敗パターンと、その具体的な改善方法を紹介します。
1. 結論がぼやけている
結論とは、その段落やセクションで最も伝えたいことの要点です。しかし初心者にありがちなのが、「当たり前」や「一般論」で終わってしまうケースです。これでは読者は「結局、何が言いたいの?」と感じてしまいます。
- 【NG】「SNS運用は大事です」
- 【改善】「SNS運用は、低コストで集客力を高める手段として特に効果的です」
結論は読者が「それなら納得」と思えるような具体性が重要です。主張には、条件・対象・理由が含まれているかをチェックすると良いでしょう。
2. 理由や根拠があいまい
理由や根拠は、読者の納得感を左右します。「なんとなく」「そういう傾向がある」では説得力に欠け、読者の信頼を得るのは難しくなります。
- 【NG】「多くの人がそう言っているから」
- 【改善】「2023年のマーケティング白書によると、SNS経由のコンバージョン率は広告より12%高いという結果が出ています」
データ・調査結果・専門家の発言など、第三者の信頼できる情報を引用することで、主張の裏付けが強化されます。特にビジネス系記事では、数値を含めた根拠があると読者の信頼を得やすくなります。
3. 例が抽象的すぎる
例は、抽象的な内容を読者に具体的にイメージさせるための強力なツールです。ところが初心者ライターは、「たとえば」で始まる文章が曖昧で、説得力を弱めてしまうことがあります。
- 【NG】「たとえば、いろいろな企業でやっています」
- 【改善】「たとえば、スタートアップ企業のA社は、X(旧Twitter)で自社商品を紹介し、フォロワー数を半年で3倍に伸ばしました」
読者が「自分にも当てはまるかも」と感じるには、具体的な数字・期間・対象名などを入れて、リアルな描写を心がけることが重要です。
読者の疑問に先回りするテクニック
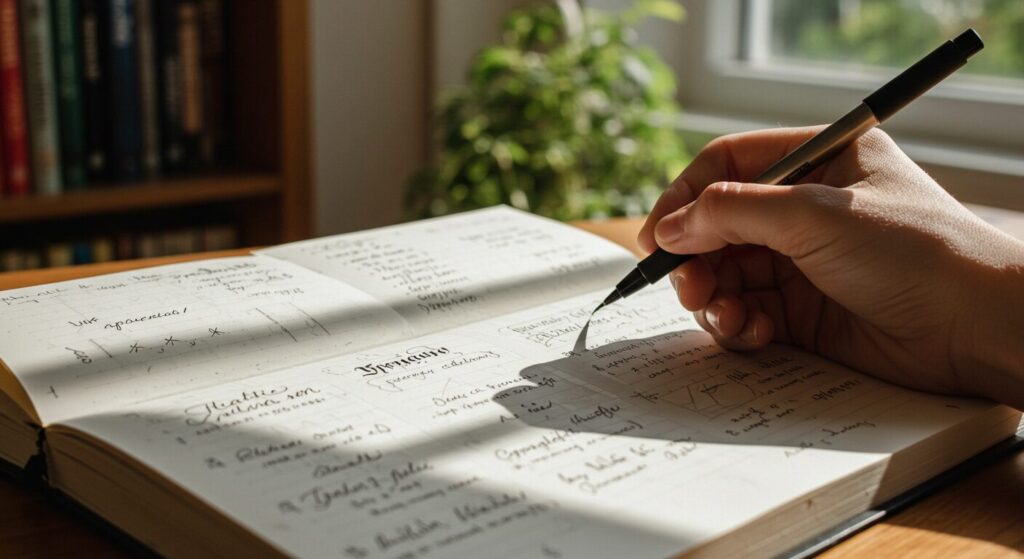
説得力のある文章を書くうえで重要なのは、読者の“心の声”を先読みすることです。ただ情報を伝えるだけではなく「この部分が気になるかもしれない」「こう思う人もいるだろう」と想像することで、読者との距離を一気に縮めることができます。ここでは、そんな“先回り力”を高めるための考え方と具体的なテクニックを紹介します。
読者の疑問は“信頼”を試すチェックポイント
本文中では、読者が「本当にそうなの?」「他にも方法はある?」といった疑問を持つ可能性があります。
単なる好奇心ではなく、筆者が提供する情報の“信頼性”や“有用性”を試す無意識のチェックでもあります。
特にインターネット上には玉石混交の情報があふれており、読者は「自分の状況に合っているか」「他の選択肢と比較してどうか」といった視点で常に情報をふるいにかけています。
つまり、読者が疑問を抱くのは自然なことであり、ライター側がその問いにどう応えるかが記事全体の信頼度を左右するのです。
疑問を放置するリスクは“信頼の損失”
読者の疑問に応えずに先へ進めてしまうと「この記事は自分には関係ない」「筆者はこちらのことを考えていない」といった感情を引き起こします。
これは、読者がページから離脱する要因のひとつです。
さらに重要なのが、こうした離脱はSEOにも直結するという点です。
滞在時間の短縮、直帰率の上昇、エンゲージメントの低下は、検索エンジンからの評価を下げ、今後の記事の露出にも影響を及ぼします。
疑問への“先回り”が信頼と共感を生む
そこで効果的なのが、“Q&Aスタイル”や“補足ボックス”などを活用した「先回りの回答」です。
記事中で読者が感じそうな疑問を想定し、それに対して丁寧な説明を加えることで、読者は「自分のことを考えてくれている」と感じやすくなります。
こうした先回りの工夫は、記事が単なる説明文ではなく、対話的で親しみのある読み物として受け入れられる助けになります。
そして読者が「この記事、まるで自分の心を読まれたみたいだ」と感じたとき、記事への信頼度は一気に高まり、共感も生まれるのです。
信頼と共感は、再訪率や記事のシェア率を高めるだけでなく、ライター自身の専門性・誠実性といった評価にもつながります。
読者との信頼関係を築くうえで、疑問への丁寧な応答は欠かせない要素です。
補足:PREP法はすべての場面に使えるの?
ニュース記事やレポートなど、結論を先に述べる必要がない場合には向かないこともあります。読者の期待する文脈に応じて柔軟に使い分けましょう。
まとめ:本文の構成で読者の納得度が変わる
本文構成の力は、文章力そのもの以上に読者の“理解と信頼”に影響を与えます。
「主張→根拠→具体例→まとめ」の流れを意識すれば、どんなテーマでも伝わりやすくなります。特に初心者にとっては、この順序を守ることで「何をどう書けばよいか」が明確になり、執筆のストレスも軽減されるでしょう。曖昧な構成は、読者にとってもライターにとっても負担となります。
この構成法は、1段落ごとに完結した意味を持たせやすく、読者の理解を積み上げながら記事を進行させることができます。読者が途中で離脱せずに最後まで読み進めてもらうためにも、情報の順序や展開には十分な配慮が必要です。
まずは1段落ずつ、この構成で練習してみましょう。